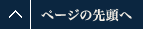「外交のカラクリ、国家の嘘」
手嶋龍一×佐藤優×田原総一朗
「オフレコ!」vol3 掲載鼎談記事
日本外務省にインテリジェンスは可能か?
田原 国家の外交や安全保障のため、主として秘密裡に――という意味は表側の外交や防衛と表裏一体に――行う情報活動あるいは諜報活動を「インテリジェンス」という。日本は、何枚かのプレート(岩盤)が地下で複雑にぶつかり合う場所だから地震が多いんだけど、地上でもアメリカ、ロシア、中国という大国の勢力圏がぶつかる場所だからゴタゴタが多い。朝鮮半島や台湾の隣で、領土問題や拉致問題はじめさまざまな懸案もかかえる。「外交は武器を使わない戦争」というが、日本のような国こそインテリジェンスがとても重要だと思う。今日はそのことを議論したいんです。そこで最初の質問。私は、佐藤優という人物を、日本の第一級の「インテリジェンス・オフィサー」と評価する。そういう人を外務省はなぜ、突き飛ばしたというか、放逐したんですか?
佐藤 その言い方には、二つの点で異議があります。第一に、私はインテリジェンス・オフィサーではない。第二に、外務省はインテリジェンスを行う組織ではない。
手嶋 僕も、佐藤さんを第一級のインテリジェンス・オフィサーだと言っているのですけれどもね。
佐藤 これは格好つけたり遠慮しているのではなくて、インテリジェンスというものは実は組織がないとできない。私は外務省にインテリジェンスをやる組織があると思っていたが、4年前(2002年)、鈴木宗男バッシングと絡んで、私と私が責任者だったインテリジェンス・チームが解体されていく過程を目のあたりにして、日本の外務省という組織には、それがないことが判明したんです。
田原 じゃあ、個人的にやっていたんですか?
佐藤 そうではありません。現役時代には私は、外務省はインテリジェンスを扱うことができる組織だと思っていた。しかし、私がいなくなると、私が育てた若い人たちについて、こいつはどこでインテリジェンス研修をした、こいつは情報機関と付き合っているということを、一部の外務省官僚がしゃべってしまった。そんな間抜けなインテリジェンス組織なんてありえない。やはり外務省に組織はなかったんだ、と。私はこれを事後的に知った。
田原 前首相の森喜朗さんに聞いたら、「佐藤さんがいなくなって、日本はロシアに対して何もできなくなってしまった」と嘆いていた。
佐藤 確かにそういう面もあります。悲しい話ですけどね。ただ私は、自分は「インテリジェンス・オフィサー」ではなくて、「インテリジェンスについて理解している外交官」だと思うんです。
田原 まあ、いいや、それでも。手嶋さん、なんでこんなすばらしい人を、外務省は突き飛ばしちゃったんですか?
手嶋 人間の世界だから、どの組織にも一種の嫉妬みたいなものがあると思うんです。
田原 手嶋さんがいたNHKにも、当然ものすごくある。
手嶋 しかし、たとえばイギリスは「老インテリジェンス大国」といってよい国ですが、そういうところは、嫉妬を乗り越えるだけの組織としての成熟度を持っている。事実、イギリスは外務省のなかに、形のうえではSIS( Secret Intelligence Service )という海外の情報収集を専らとするインテリジェンス組織を組み込んでいます。外務省本体の外交一般に関する情報と競合させている。外務省の本体は、時にSISに出し抜かれても、嫉妬に耐える懐の深さを持っているんです。
佐藤 日本外務省について率直に申し上げれば、川島裕さんが外務事務次官(1999~2001年)をやっていたときは、そういう発想ができた。トップに立つ人が誰かということが、非常に関係していると思うんです。
田原 竹内行夫(2002年2月~2005年1月まで外務事務次官)なんて人は、どうしようもない?
佐藤 竹内さんという人は幅が狭かったと思う。それから、なんで鈴木宗男さんにあんなにすり寄るのかなあと、いぶかしいほどすり寄った。
田原 土下座したなんて、鈴木宗男さんは書いている。
佐藤 私が目撃したときは、床から30センチくらいの低いテーブルに、両手をついて深々と頭を下げた。これがまた、おもしろいんです。大江博という条約局条約課長(2000年4月~2002年8月)がいて、「竹内さんは決して鈴木さんに逆らっているわけではないです。竹内さんは今後、次官になる人材です。決して逆らうつもりはありません」という。深々と頭を下げる場面で、部下にそう言わせるんです。見ていて「大丈夫かな、この組織は」と思ったんですけど、やはりダメでした。そういうことを絶対やらない人もいる。現・外務省事務次官の谷内〈ヤチ〉正太郎さんがそうです。鈴木さんにおもねっておべんちゃらは絶対に言わないし、鈴木叩きの時にも一切加わらない。ある意味でとても「官僚道」をわきまえた人です。
田原 そうか、谷内さんは加わらなかった。「吏道」という言葉があるが、官僚としての分限や節度をわきまえた人が、外務省に皆無ではないと。
佐藤 谷内さんは鈴木さんとぶつかったことがあるにもかかわらず、鈴木叩きに加わらず、田中真紀子さんにもすごく忠実に使えたわけです。しかし、田中さんにも過度にすり寄ることはしなかった。これはインテリジェンスの本質的な話に関わると思うんですが、谷内さん個人が突然変異なのではなくて、「谷内正太郎的なるもの」が外務省という組織の遺伝子としてちゃんとあるんです。その遺伝子を受け継ぐ人がトップになれば、インテリジェンスができる。
田原 今は、なんとかできている?
佐藤 できる体制はあると思う。ところが体制はあっても、今度は人材がいない。前は人材はいたが、体制がなかった。この巡り合わせが難しい。
CIAもSISもぶっちぎった佐藤優
田原 佐藤さんは、02年5月に背任容疑で東京地検特捜部に逮捕された。テルアビブで開いた国際学会への代表団派遣費用を外務省関連組織(支援委員会)に不正に支出させ、3350万円の損害を与えた容疑ですね。ところが、その支出の決裁書には、佐藤さんの上司である東郷和彦さん(当時・外務省欧亜局長)はじめ上の人びとがハンコをついた。佐藤さんによれば次官の決裁まで取り、次官がサインした決裁書が間違いなく存在するが、公判で外務省からはそれは出てこなかったと。東郷さんは、いまだに海外を逃げ回っている。手嶋さん、どう思いますか?
手嶋 まず外交ジャーナリストとして、この裁判の核心部分を押さえておきたく思います。一審の判決は、二つの論点から成立しています。まず、イスラエルでの学会に国の予算を支出した行為は、日ロ間の協定に違反している、と判断しています。そのうえで、支出に当たっても不正が行われた、というものです。外交ジャーナリストの守備範囲として、もっぱら第一の点だけを論じます。二国間の条約、多国間の協定、さまざまな口頭了解。これらの国際約束が、適当なものかどうかを判断するいわば有権解釈権は外務省にあるとされてきました。具体的には、次官、条約局長、条約課長にその判断が委ねられてきました。この点については、外務省内にとどまらず、全盛期の大蔵省ですら認めてきたことです。具体例をひとつだけ挙げておきます。日米半導体協定(1986年に第一次協定締結)がそうです。当時の通産省は、アメリカと非公開の一種の密約を結ぼうと試みました。しかし、外務省条約局、とりわけ一係官が、密約は戦後の憲法の精神に触れるとして、頑として認めようとしませんでした。
田原 でも、それらしいことは盛り込みましたよ。
手嶋 その通りです。ですから、密約という批判をかわすため、「サイドレター」として姑息にも処理したのです。後に、このサイドレターが国際的なコミットメントにあたるかどうかで、日米間に論争が持ち上がり、相互不信を高めてしまいました。この事からもわかるように、条約や協定の解釈・運用にかかわる外務省条約局の権力は強大なのです。さて、日ロの協定に基づいて、支援委員会に予算を支出してテルアビブでの国際会議の費用をまかなえるかどうか。ここで、外務省の条約局に判断が求められました。結論を申しのべます。条約局は、日ロの協定に基づいてイスラエルでの国際会議に予算を支出するのは合法という判断を下しています。事務次官、条約局長、条約課長がそろってそれぞれの書類に決済の署名をしています。「適法」と判断した、これら関係者の調書もあるといわれます。にもかかわらず、一審の判決は「協定に違反して」となっています。「なぜ、協定違反なのか」については、説得力のある判断が示されていません。仮に、協定違反だとしたら、罪に問われるべきは、担当の事務官ではなく、有権解釈を下した外務省の首脳そのものです。首脳陣が決済した判断に従って実務を行って罪に問われるなら、そんな国に勤める役人など一人もいなくなってしまう。判決の前段がすでに破綻しているのです。
田原 つまり、無茶苦茶な話だ。その国際会議を認めて開催したって、迷惑を受けた国民は一人もいない。役所が危ない薬や建物を認可したら国民に死者が出たという話とは、まるで違う。仮に国際会議がまったく無意味でカネのムダ遣いだったとしても、無意味なシンポジウムを開いたりムダな道路やダムを建設したお前が悪いと、逮捕された官僚なんていない。そういう外務省って、何なのか?
手嶋 僕は、ことさら佐藤優さんのサイドに立って発言しているわけではありません。イスラエルが対ロシア情勢の収集について重要な位置にあることを、ワシントンにいた僕はよく知っていました。「対ロ情報の出口としてのイスラエル」という日本外交における未開の分野を開拓したのが、「怪僧ラスプーチン」こと佐藤優さんだった。だからテルアビブで国際会議を開き、対ロ情報を収集する土台を固めるのは当然のことです。具体的な成果も上がっていた。日本の対ロシア、対クレムリン情報収集の上で、特筆すべき動きといっていい。
チェルノムイルジン首相が更迭(1998年3月)される以前の時点で、クレムリンが首相更迭の決断をしたと知っていた人物は、まさに更迭を決めた大統領を含めて、一握りだったはずです。日本はその極秘情報をイスラエル経由で入手した。アメリカもイギリスもまったく知らなかったのです。それを可能にしたのが佐藤優という優れたインテリジェンス・オフィサーだった。この情報ルートは、かつてスターリン批判をはじめて行った「フルシチョフ秘密報告」が『ニューヨークタイムズ』にスクープされるに至るルートと大枠で同じです。だから、イスラエルで国際会議を開くことにはなんら問題がない。むしろ、もっと頻繁に開くべきだったと僕は思います。
なぜ、佐藤ラスプーチンはクレムリンに潜入できたか?
田原 佐藤さんは、なぜ米CIAも英SISも知らなかった重要機密を握りえたのか? そもそも、なぜラスプーチンと呼ばれているのか?
手嶋 ラスプーチンというのは、当時外務省に圧倒的な影響力を誇っていた鈴木宗男さんに取り入って、その最大の権力者を操り、そのことによって日本外交全体を牛耳っていたという壮大なお話。まさにロシアの怪僧ラスプーチンだというのでしょう。
佐藤 それは、あと知恵の世界です。私のことをラスプーチンと命名した人は、現実にいるんですよ。実は、鈴木宗男さんです。鈴木さんは私が逮捕される直前、「俺がラスプーチンなんてアダ名をつけちゃったから、迷惑かけたなあ」といっていましたが。鈴木さんはロシアのことをよく知っている。ロシアでラスプーチンは、必ずしも悪いイメージではない。彼は硬直した官僚制度のもとで真実が伝わらないとき、皇帝のところに行って「民衆は戦争反対です。帝政に対する不満が高まっています」と本当の姿を伝えた。そんな民主主義者としてのイメージもあるんです。そのラスプーチンの話を聞いた鈴木さんが、「あんたはクレムリンの奥深くまで入って、すごい人脈を持っている。怪僧ラスプーチンみたいだ。ラスプーチンさんと呼ぼう」とつけたアダ名なんです。
手嶋 すると、この『オフレコ!』鼎談は、なかなか面白い役割を果たしたことになる。「佐藤優=ラスプーチン」説には二通りの解釈があることを明らかにした。さっき僕がいったのは多数派というか、正統派の解釈です。ご本人が言っているのは少数派にして異端派の見立てです。これでラスプーチン命名をめぐる謎を解くきっかけがつかめた。
田原 佐藤さん、どうすればクレムリンの奥深くまで入れるんですか?
佐藤 私は田原総一朗さんを「権力党」のメンバーととらえている。権力党というのは自民党とか民主党とか、かつての新進党とかには関係ない。つねに権力というものはあるんですが、その中枢に近いところにいる人びとが、私のいう「権力党」。これは権力におもねっているという意味ではありません。私は、田原さんはすごいインテリジェンス感覚を持っていると思いますよ。
田原 ちょっと待って。権力って、おもしろいものだ。
佐藤 その通りなんです。私は、おもしろかったんです。あんまりおもしろいので、好奇心にしたがって真実を知りたい、誰も知らない本当のことを知りたいと思った。モスクワにいるジャーナリスト連中には負けたくないし、ロシア人エリートがクレムリンについてあれこれ言う以上のことが知りたい。そんな好奇心が一番大きかった。好奇心ともう一つ大切なのは、約束を必ず守ること。裏返すと、できないことは約束しない。それを積み重ねていたら、いつの間にか「けもの道」みたいなところを通って、クレムリンのエリツィン大統領の隣の部屋で座っている、という感じになっちゃったわけです。田原さんがいつの間にか首相と話しているのと、あんまり変わらないんじゃないですか。
インテリジェンス・オフィサーか、ジャーナリストか
田原 手嶋さんに聞きたい。『ウルトラ・ダラー』を読んで、手嶋さんは「ジャーナリスト」より「インテリジェンス・オフィサー」というべきじゃないかと思った。どうですか?
手嶋 先ほどの田原さんは同じような質問を佐藤さんにしていましたね。私もラスプーチン流に答えさせていただきます。「自分はインテリジェンスに関する知識を少しだけ持ったジャーナリストにすぎません」と。
田原 では、インテリジェンス・オフィサーとジャーナリストは、どこが違う?
手嶋 インテリジェンス・オフィサーは、国家からおカネを貰い、国家のために極秘の情報を集める。僕らジャーナリストは、あまねく一般からお賽銭をいただき、その情報をみなさんに還元する。この定義でいいですか?
佐藤 その通りです。
田原 ちょっと違うと思う(笑)。手嶋さん、集めた情報を全部は報道してないでしょ。全部一般に戻しちゃったら、アメリカの政府高官にそんなに信用されない。
手嶋 それは確かにその通りです。僕は、どちらかというと「すぐには書かない記者」なのかもしれません。けれども、長期的にみれば、はかなりの部分はちゃんとみなさんに還元しているつもりです。正直に申しあげると、僕は比較的にタメのある記者です。その意味では、鵜飼いのようにすぐには情報をはき出さない。
田原 なるほど。「鵜飼いの鵜」じゃないぞと。それはいい喩えだな。日本のメディアには鵜飼いの鵜みたいな記者が多すぎる。
手嶋 一面では、それは組織に対する、たとえば僕が所属していたNHKに対する忠誠心が低いとも言えるでしょう。しかし、組織のなかで自分はどうしようとまったく思ったことがない。NHKにいたときは、たしかにNHKというメディアを通じて視聴者に情報を還元し、いまは本や雑誌、小説を通じて読者に還元しています。いずれにせよ長期的には一般の方々に情報は返っていくものだと思います。
田原 手嶋さんは、ジャーナリストあるいはジャーナリズムを「焼き畑農業」といっていますね。これはどういうこと?
手嶋 ジャーナリストが知的な補給をまったくせず、一日十何時間か夜回りから朝がけをして情報を取り、一方、記者クラブでは、おびただしい数のろくでもない官製の発表に付き合い、縦のものを横にするだけのような記事を書いていたら、10年もすればたいていの記者は干からびてしまいます。これではメディアの焼畑農業です。
外務省は歴史を隠蔽し、はては偽造しかねない!
田原 佐藤さんも手嶋さんも私も、ある意味で「けもの道」に踏み入った。そこで聞きたい。1972年の沖縄返還のとき『毎日新聞』の西山太吉記者が日米間の密約をスクープした。しかし、彼は外務省の事務官と情を通じて情報を取ったとして逮捕された。情報は「情け」ある「報せ」と書くけれども、「情事」で「報せ」を得たと。彼の分け入った「けもの道」は、どうですか?
手嶋 西山記者は、女性と付き合うことで情報を入手した。西山記者は、この点を批判されました。が、そんな小さな倫理を越えた、大きな大義のために、時に批判を甘受しても貴重な情報を入手しなければならない局面があるかもしれません。たとえば、戦争か、和平か、という岐路で、戦争を回避するためにジャーナリストが女性と親しくしても、さして問題にはならないでしょう。西山さんの場合、致命傷だったのは、自分で『毎日新聞』を通じて報道すべきだったところを、情報を国会議員に渡してしまったことです。ですから、私は、西山さんのすべてを支持するわけにはいかない。
田原 『毎日新聞』で報道していれば、支持できる?
手嶋 取材方法には、感心できない部分が残ったものの、国家の密約をあばくという点では理解できる側面もあると思います。
田原 佐藤さんに聞きたい。アメリカは、他国と密約を交わしたら時期を置いて公開しますね。日本はしない。西山さんのあばいた密約(沖縄の土地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりするとの内容)も、日本政府は「そんなものはない」と否定していた。ところがアメリカが公文書を公開したから、政府の言い分が間違いだとわかった。なぜ日本は時期を置いて公開しないんですか?
佐藤 私、今そのことで外務省から脅されているんです。私は『日米開戦の真実――大川周明著「米英東亜侵略史」を読み解く』という本を書いた。その中で「国家は、必要なときは嘘をつく。だが、嘘をついたという記録だけは残しておき、いつかその嘘は国益に害がないと明らかにしなければいけない。沖縄返還の密約に関しては、アメリカで文書が出てきた。沖縄返還協定(1971年)当時に外務省アメリカ局長だった吉野文六さんも、自分は嘘の証言をしたと語った。この期に及んでも外務省が嘘を突き通していのは問題だ」と書いたわけです。ところが、これが外務省の「検閲」を通らない。絶対に削除しろと。
田原 佐藤さんが書くものに検閲があるんですか?
佐藤 外務省には寄稿届という制度があって、事実上検閲機能を果たしています。起訴休職中の外務省職員である私は、遵法主義だから全部寄稿届を提出しています。すると外務省から「絶対に削除ありたい」と要請書がくるわけです。私は「これは無視する。どうぞ処分なさい」と外務省に言っているんです。もちろん処分したら争います。
手嶋 沖縄密約の場合は、吉野文六証言にあるように、記録そのものは外務省の然るべきところに残っています。ところが公的な記録が残っていないケースがあるのです。僕はその闇を『ウルトラ・ダラー』で書いたわけです。金丸訪朝以降、小泉総理の平壌宣言にいたる一連の対北朝鮮外交の記録、ミスターXとの折衝を含めた公的な記録がどこにもありません。僕は外交ジャーナリストとして、これだけは断じて容認できない。国益のために、その時は公にしない。公言できないケースは確かにあるでしょう。しかし、それに関わった当事者が公的な記録を残さないことなど許されていいわけがない。こんな事態は、日本以外に、スターリン統治下のソ連でもなかったはずです。
佐藤 それは、官僚の義務というかルールの大変更になってしまいますからね。
田原 だけど、現に秘密を公開しないんでしょう、日本政府は?
手嶋 公開しないのみならず、記録自体を公開したくないという理由で残さない。
佐藤 公開しないだけなら、まだいい。問題は当時外相だた川口順子さんが「(2000年に当時の河野洋平外相が)吉野(文六)元局長に話をされて、密約は存在しないということを確認済みでございます」(2002年7月4日の参議院外交防衛委員会)と国会答弁で嘘をついたことです。元アメリカ局長が証言したにもかかわらず、外務省が調べもしない、この不作為です。こういう積み重ねは国益を損すると思う。だからこの問題については、事実を明らかにする以外の道はない。
手嶋さんが、必ず残さなければならない記録を残さないから、歴史の事実が確定しないとおっしゃった。そこで留まっているならまだしも、重要な事実を書かないような組織は、次の段階で必ず嘘の報告書を作ります。それで国民に嘘の歴史を残すことになったら、これは大変なことになる。いま外務省のモラルはそこまで落ちかけているんです。
田原 自分たちに不都合な秘密を隠すどころか、歴史を偽造する。これは大問題だ。自分たちが隠していたこと、ときに間違ったことも含めて、それが歴史ですよ。みんなで本当の歴史を編んでいって、よりよい未来を築くという発想が、なぜできないんだろう。ちょっとテレビ局なんかも似たようなところがあって、古いVTRなんかバンバン捨てちゃうし、記録を残さない。自分たちがかつてやってしまった誤報とかやらせとか、膨大な記録を残せば、同じような過ちは減るはずですね。しかし、記録を捨てちゃったら同じことの繰り返しになってしまう。
平壌宣言の「取引」を国民は支持したか?
田原 ところで、平壌宣言についてお二人に聞きたい。小泉純一郎さんが北朝鮮を二度訪問した。あの意味は何だったのか? 成功だったのか、失敗だったのか?
手嶋 僕は、基本的には決して成功だったとは言えないと思います。なぜならば、僕は世界中さまざまな人と会ったり、その言説に触れたりしていますが、平壌宣言を肯定的な文脈で引用した人に一人も会ったことがないし、そんな主張も読んだことがない。
田原 肯定的でないというのは、核の問題がダメということ?
手嶋 核の問題も含めてです。
佐藤 あれは、取引文書ですね。明らかな取引。素直に読めばいいと思うんです。「北朝鮮が拉致問題を解決し、大量破壊兵器の開発をしないと約束するならば、日本はおカネを出します」という取引文書です。
田原 取引文書だからダメなの?
佐藤 いや、取引だからダメなのではない。明かな取引文書だが、そのことを日本人が理解しているかどうかが問題です。もちろん小泉さんは理解していると思う。しかし、取引の内容が、国民によって支持されるものかどうか。取引内容の大枠、その基本的なコンセンサスについて国民的な議論をするのは、国会で議論するということですね。そういった手続きを十分踏まえたのか。外務省のなかでも外交専門家たちが「この取引でいいんだ」というコンセンサスをもってやったかどうか。
手嶋 外務省のなかでも、コンセンサスは明らかになかったですね。条約局の役割についてお話しましたが、良くも悪しくも条約局というものが、戦後の日本外交を支配してきたのです。外交当局は、少なくとも国際約束の運用ついては有権解釈権を持ち、その点では絶大な影響力を持ってきました。大蔵省や通産省すら風下に立たせていたわけです。冷戦期は外交案件でしばしば国会の予算委員会が止まる。与野党攻防の最後のよりどころ、つまりゴールキーパーは、外交の場合は内閣法制局ではなく、外務省条約局でした。だから条約局長には、そのときどきで最強打者が送り込まれていた。ところが、平壌宣言には条約局がほとんど関与していない。条約局長が訪朝そのものを初めて知ったのが2002年8月21日前後。話が公になるのは8月末ですが、平壌宣言の文案はすでにかない詰まっていた。
田原 関与の有無はともかく、条約局は結局、平壌宣言を認めたわけですね?
手嶋 事実上そうです。
田原 言い分があっても黙って認めたなら、条約局がだらしないんじゃないですか?
手嶋 その批判は甘受すべきでしょうね。
田原 小泉さんが二度訪朝した後、薮中三十二さんと佐々江賢一郎さんが交渉に行く。当時、私は彼らに取材したけど、あの交渉は成功だったと言い、小泉さんも手応えありだと言っていた。ところが、その直後に、横田めぐみさんの遺骨が偽物とわかった。あれは、欺された日本の外務省がバカだという話ですか?
佐藤 たんなるバカなら話は簡単なんですけど。ようするに北朝鮮側の内在的論理を汲みとれていない。北朝鮮の外務省と人民保安省の関係を正確に理解できていない。非常に初歩的な、公開情報をベースとする交渉相手の組織の認識すらできないまま、準備不足・訓練不足で行ったんだから、バカよりたちが悪いです。
田原 なんですか、それは? 公的な対外窓口である北朝鮮外務省と、拉致に関与した一種の諜報機関、特殊工作機関である人民保安省の関係がわかってない。外務省が人民保安省を完全にコントロールするとか、両者で調整をつけることはありえないのに、北朝鮮外務省と交渉し約束を取り付けたつもりの日本外務省は、バカに輪をかけたバカだと?
二度の小泉訪朝、平壌宣言は日本外交の失敗だ
佐藤 そう、外交の世界で無能は犯罪です。ちょっと話を戻したほうがよいですね。私が見るところ、朝鮮半島に平和を作り出そうというのが平壌宣言の基本哲学です。そして、私はこの基本哲学が間違いだと思います。朝鮮半島が平和であろうが戦争であろうが、日本にとって、一般論としては戦争より平和がよいという以上の意味はない。なぜわれわれが北朝鮮と取り組まなくてはならないかというと、朝鮮半島に平和をもたらす必要があるからではなく、拉致問題が存在するからだと私は思います。拉致事件は日本人の人権が侵害されたのみならず、日本政府の国家の領域内で平和に暮らしていた日本人が北朝鮮の国家機関によって拉致されたという、日本国の国権が侵害された事件です。日本人の人権侵害と日本国家の国権侵害を原状回復できない国家というのは、国家として存在する意味がないんです。
手嶋 佐藤さんがいうように、北朝鮮問題の最大のものが拉致問題ならば、それは平壌宣言の中軸に書かれていなければならない。しかし、まったくそうなっていない。だからこそ、ピョンヤン宣言を肯定的に引用する国などないのです。
佐藤 だから、平壌宣言が示す取引の何が問題かというと、目的と手段が逆転していること。目的は拉致問題の解決で、それ以外のことは手段でなければいけない。ところが平壌宣言は、拉致問題と大量破壊兵器の問題が解決すればカネを出すという手段を使って、日朝国交正常化を果たし、朝鮮半島に平和を実現することが目的なんです。
田原 それは小泉さんも宣言した。二度目の訪朝のとき北朝鮮での会見で「私は日朝国交正常化のために来た」と、こう言った。
佐藤 その「日朝国交正常化のため」は、小泉さんの内在的論理では「拉致問題の解決のため」なのか、それとも「朝鮮半島に平和を作るため」なのか。
田原 朝鮮半島の平和のためでしょう。そうじゃなかったら、小泉さんは拉致問題を解決に来たんだと言うべきだった。ところが、彼は日朝国交正常化のために来たんだと言った。そう言わせたのは、外務省も官邸も、それを認めたからでしょう?
佐藤 いや、私の解釈は違います。レトリックの問題として、日朝国交正常化に拉致問題が完全にくっついて、不可分の関係になっているならば大丈夫だと小泉さんは思ったのでしょう。しかし、外務官僚が作った文章はそういう構成になっていない。
手嶋 田原さん、ここが問題なんです。平壌宣言の主要な骨格は、まず日朝間で国交正常化をし、日本国民の税金を使って北朝鮮に経済協力をするということですね。国交正常化の前提条件として、大量破壊兵器(核)の問題と拉致の問題があります。とこれが、核の問題は一応書かれていますが、拉致の問題は宣言には書かれていない。これほど重要な拉致問題を平壌宣言に書き込ませる情勢にはなかったにもかかわらず、小泉首相は平壌宣言に署名してしまった。国内世論や国際世論を甘く見てしまったのでしょう。
佐藤 おっしゃる通り。
田原 ただね、拉致の問題、工作船の問題、金正日がいろいろ認めたわけですね。小泉さんは、「認めたんだ。だからいいじゃないか」と言っている。
佐藤 いや、「だから、いいんじゃないか」とまでは、小泉さん言っていないでしょう。
田原 なんで? だって認めたからこそ、小泉さんは平壌宣言を出したんでしょう。
手嶋 先方が本当に認めたなのなら、その事実を平壌宣言にきちんと書かなければいけない。ああいう国です。言を左右にしたりするのは常識なのだから。にもかかわらず書かなかった。そのつけがいま出てきている。核疑惑もいっそう深まっている。ミサイルの発射を凍結したということになっているが、発射しないという保証はないことは現下の情勢で明らかです。平壌宣言はその日のうちに空中分解してしまう。
田原 だから、小泉さんの二度にわたる訪朝は失敗だったと。
手嶋 おおいに疑義ありと申し上げていいと思います。ノドンやテポドンが発射された段階で、宣言自身が吹き飛ぶ。僕だけが吹き飛ぶと言っているのではありません。麻生太郎外務大臣が、もし仮に北朝鮮がミサイル発射をするようなことがあれば、平壌宣言そのものが無効になるときっぱりと発言しているんです。これは、小泉総理の下で外交を担当する責任者の発言ですよ。
佐藤 外交は大学のゼミじゃないから、相手を論破するだけでは意味がない。われわれ外交の実務にたずさわった人間は一つの病気にかかるんです。それは「失敗って言えない病」です。どんなことがあっても、何か引っかかりがあれば、そこから日本の国益をプラスの方向に持っていけないかと考えてしまう。だから、誰も失敗とは指摘しない。しかし、これまでの日朝交渉は、日本側が目標とした成果がほとんどとれていない。客観的に見れば、明らかに失敗でしょう。
田原 めぐみさんの遺骨を本物と信じていたら偽物だった。どうするんだというとき、当事者だった薮中さん佐々江さんは異動になってしまう。実に無責任ですね。どう思う?
佐藤 外務省は、組織として終わっています。外務省は責任をとらない組織になってしまった。これはソ連共産党中央委員会とそっくり。絶大な権限はあるんだけれど、責任は負わない。官僚というのは、放っておくとそうなってしまう。
田原 大蔵省(現・財務省)もそうだ。
佐藤 責任を取らせるには、政治が手を突っ込まないかぎり絶対無理なんです。ですから政官の癒着が問題だ、政治家はろくでもないんだと遠ざける結果、自動的に官僚にフリーハンドを与えることになってしまうんです。
対韓外交を勝利に導いた谷内正太郎という男
手嶋 官僚は、失敗を認めず、責任を取らない。それが官僚組織の鉄則です――これは一般的にはそうなんですが、反証の材料が目の前にあります。竹島問題をめぐる日韓の交渉がそれです。竹島問題で両国の緊張が高まった4月、谷内正太郎外務事務次官が突然訪韓して交渉にあたりました。田原さんの番組で「どう評価するのか」とお尋ねがありました。私はかなり思い切ったことを申し上げた。「あの局面では日本国として、谷内カードを切るしかなかった」と。カードを切った政治家の側が、どれほど自覚していたかどうかは知りません。が、もしこの交渉が不首尾に終わったときには、責任を取るはずがない官僚が責任をとるつもりだった、と私は見ていました。それほどの覚悟でソウルに行ったのでしょう。現在の日韓関係は、首相や外相、いわんや政務官や副大臣など政治家が行って交渉できるほど生易しいものではない。国際法に精通した外務官僚のトップがいって、打開するほか、他策はなかったのです。谷内次官は、二つのことをとりまとめてきた。一つは、日本が海洋調査船を出すことを中止し、韓国側も韓国名の表記の提案をやめる。もう一つは、日韓の排他的経済水域(EEZ)交渉を再開し、話し合いをする。この二つ目が極めて重要です。韓国側が実効支配をしていると主張している領土を交渉のテーブルにのせると約束したのです。係争中の領土問題ではありえないことです。
佐藤 島を実効支配している側が話し合いに応じるのは、領土問題の存在を認めるということだから、日本にとってたいへん有利な話なんです。直後に私は『フジサンケイ・ビジネスアイ』に「対韓外交の勝利」という記事を書いた。これは日本外交の久方ぶりの勝利であると。
田原 そうか。韓国は竹島は自分のものだといい、警備隊まで置いているわけだから。
佐藤 韓国にすれば、一切取り上げなければいいわけですよ。それが「竹島はわが国固有の領土だ」と言う日本はけしからんと。じゃ、韓国はそちらの言い分をお書きなさい、日本もわれわれの言い分を書きます、という入り口まで谷内さんは持っていった。1964年の日韓基本条約はもとより「紛争に関する交換公文」にだって、竹島問題なんて一言も書いてない。それを戦後初めて、竹島を外交問題としてフィックスできる状況の直前まで持っていく。韓国のナショナリズムを逆用し、外交官としての谷内さんの非常に上手な計算が働いた。
手嶋 「勝った者は決して白い歯を見せてはいけない。なぜならば、相手側が譲りすぎたことに気づき、交渉に禍根を残すからだ」とは、ビスマルクの言葉だとも言われています。谷内次官がやったことは、まさにこれ。一日目は厳しい交渉だったと一貫して言い続け、二日目もよい表情を一切見せずに終わった。交渉直後に出た週刊誌は『週刊新潮』も『週刊文春』も、総理秘書官のコメントのようですが、「譲りに譲り続けた国賊だ」という批判を載せて、ナショナリズムとい名の劣情を刺激した。日露戦争以降そのナショナリズムで国を誤ったことは小学生でも知っているはずです。だが、とりたてて反論もしなければ、言い訳もしない。ふつうなら、ついうれしくなって「実は勝ったんだ」といってしまいます。それは尋常ならざる交渉者なのです。もっとも、よい人か悪い人かというと非常に悪い人ですけれども……。
佐藤 それは悪い人でしょう。
田原 悪い人じゃなきゃあ、よい外交官が務まるはずがない。
佐藤 そうです。あまり誰も言わないから、私が書いたんですよ。韓国がそれを結構引用している。私が書いたのは、ようするに今回は日本外交の勝利なんだ。谷内さんは、さっき話したように一種の「官僚道」を持った人ですが、今回は外交の技法から見た場合に、非常に立派なことをした。実効支配ができていない領土問題を、外交の土俵にのせるというのは非常に重要なんだと。そう書いたら、外務省の中で「佐藤は谷内を誉め殺しにしている。谷内を潰そうとして誉めている」という話が出た。
田原 へぇ、ほとんど病気だね。
佐藤 だから翌週、続けて書いた。私は、渡辺幸治・元ロシア大使から「谷内だけには気をつけろ。後ろから平気で人をバッサリ斬れる人間だ。瀬島龍三仕込みだ」と言われたことがある。あとで調べてみると、谷内さんは外務本省の訓令に反し、アメリカとある経済交渉をまとめたことがあった。激怒した当時の外務省幹部が「こんな横紙破りは叩きつぶせ」と谷内さんを依願退職に追い込もうとしたのを、瀬島さんが「谷内は国益のため必要だ」とたしなめたということのようだ。この一件が示すように、谷内さんは自らが国益と信じる道を、自己保身を排しても進む外交官です。そういう外交官が少なくなってしまったことは寂しい。誉め殺しとか、陰で佐藤は谷内と手をつないでいるんじゃないかとか、そういうデマを流す外務官僚は浅ましいと、私は書いたわけです。
イラク戦争を主導したネオコンとは何か
田原 ここで話題を変えて、イラク戦争について話したい。アメリカはイラクで手を焼いている。これはアメリカの何が原因なのか? アメリカの欠陥はどこにあるのか?
手嶋 やはり、情勢を見誤ったと思うんです。
田原 インテリジェンス・パワーに欠けていた。
手嶋 それも含めてです。僕も、ブッシュ政権のイラクへの力の行使には反対でした。私どもワシントンに在ってホワイトハウスの動きを見ているジャーナリストは、ほとんどの場合、アメリカの力の行使に反対するものなのです。国際世論が、強大な力をもつ超大国の軍事力の行使に厳しい監視の眼を注ぐ。それでようやくバランスがとれるのです。なぜならアメリカ大統領が軍事力の行使に踏み切ると、アメリカの世論はほぼ例外なくそれを支持します。政権の支持率はグーンと跳ねあがる。政権の浮揚力を高めようとすれば、つい力の行使に傾いてしまうのです。だから伝家の宝刀を抜きがちです。しかし、かつてのベトナム戦争がそうであるように、力を行使すれば必ずどこかで毒が回ってくる。だから、われわれメディアは、アメリカの力の行使にはいかなるケースであれ、慎重には慎重を期すべしと主張すべきなのです。
それでも、ブッシュ政権寄りではないかという批判を受けることはあります。が、力の行使を支持したことはありません。その一方で、戦局の通しを述べよと言われたときには、バクダッド攻略は非常に簡単だと指摘しました。実際その通りになった。その部分だけをとりあげれば、米軍に沿った見解だと思われたかも知れません。しかい、バクダッドは簡単に陥落しても、イラクの治安を回復し、イラクを中東の不安定要因から脱却させることは極めて難しいとかならず指摘してきました。ブッシュ政権は、明らかに自らの力の過信をしてしまいました。
田原 ブッシュは、なぜ過信した?
手嶋 イラクへの力の行使に、ブッシュ大統領を連れて行ったのは、チェイニー副大統領やラムズフェルド国防長官ら強硬派といわれる人たち。さらには、イスラエルの利害により寄り添った「ネオコン」(新保守派)と呼ばれる人たちです。ネオコンには三つの定義がありますが、その一つは、民主党を含めたリベラル派が力の行使をためらうのに落胆して、リベラルから保守に移った人たちでその大半がユダヤ人。ウォルフォウィッツ前国防副長官がその中心です。さらには「闇のプリンス」と呼ばれるリチャード・パール(レーガン政権で国防次官補)のようなイディオローグたちです。たとえばウォルフォウィッツは、両親を除くほとんどすべての親族をアウシュビッツで亡くしている。彼らネオコンをイラク攻撃のメインストリームに押し出したのが、あの2001年9・11の同時多発テロ事件でした。もちろん、最後の政治責任は大統領たるブッシュさんが負わなければいけないし、いま負いつつあるんだと思います。
アメリカは民主主義を他国に押しつける侵略者
田原 佐藤さん、アメリカがイラク戦争を仕掛けた理由の一つは、フセインが大量破壊兵器を隠しているから、もう一つはフセインはビンラディンと、つまりアルカイダと組んでいるからだという話だった。しかし、二つとも事実ではなかった。これはなんですか?
佐藤 二つめの話が最初から大嘘だというのは、ちょっとでも中東やイスラムの歴史を学んだらわかるはずです。ビンラディンたちの考えは、イスラム原理主義の帝国を作るということで、民族や国民国家の意味はない。一方、フセインの考えはイラク人による大国民国家を作るということで、これは基本的に民族主義の亜流です。だから、フセインはビンラディンの仲間をたくさん殺しているし、ビンラディンにとってフセインは打倒の対象なんです。強いて共通点を挙げれば、アメリカとぶつかっていることだけで、あとは全然つながらない。しかし、子どもでもわかる大嘘なんだけれど、くっつけてやれと意図的なわけですね。やっつけることを最初に決めていたからで、それはネオコンと関係していると思います。
田原 大嘘とネオコンが、どこで関係する? イスラエルということ?
佐藤 イスラエルなんだけど、ネオコンのもう一つの要素は、アーウィング・クリストルが書いた「ネオコンサバティズム」という論証を読むとはっきりする。かれらはニューヨーク市立大学出身のトロツキストグループなんです。
田原 何だって? トロツキスト?
佐藤 そうなんです。だから、学生時代の世界革命の思想持っているわけです。かれらが民主党に行ったときも、現在もその思想は変わっていません。ただそれは、マルクス主義に基づく世界共産革命ではなくて、世界自由民主主義革命なんです。だからネオコンというのは、独裁者や悪いやつはやっつけて、普遍的な一つの理念で世界を統一していこうという革命家たちなんです。
田原 でも、イラクに民主主義を軍事力で押しつけるのは、イラクへの侵略ですね。
手嶋 まさに、アメリカとは、そういう国なのです。理念の共和国といわれるゆえんです。義を見てせざるは、というわけですが、まことにおせっかいな国なのです。
佐藤 そうです。旧ソ連がハンガリー人民共和国や、チェコスロバキア社会主義共和国に軍事介入した時も、侵略ではなくて同志的な援助を差し延べるという「大義」があったというわけです。
田原 「プラハの春」なんかに戦車を出して介入し、つぶしたのもね。ソ連は援助とそう言ったが、アメリカ側に立つ日本は、これは侵略だと思っていた。ところが今は、ソ連と同じことをアメリカがやっていると。
佐藤 そういう図式です。
手嶋 大半のアメリカ人は、アメリカという国は丘の上に燦然と輝く民主主義国家だと信じている。その自由の理念が正しいならば、それを世界にあまねく、とくに独裁政権下にある人たちに伝えなければいけない、という伝道者のような使命感に駆られてしまうのです。
田原 伝えるのはいいけど、軍事力で現政権を破壊するというのは、やりすぎだ。
手嶋 だから、他国とその政権を破壊しているという意識がないでしょう。
佐藤 普遍主義的なものの考え方の特徴で、世界一だと思っている人は、自分の感覚は世界の常識だと思ってしまい、それを世界中に善意で押しつける。市場原理主義もネオコンの自由民主主義革命路線と一緒だと、私は見ています。
軍事力が強大だと、情報力は弱くなる
田原 「グローバル・スタンダード」という名のアメリカ標準の押しつけですね。手嶋さんがいうように、ブッシュ政権の情報はあやふやだった。そのあやふや情報に基づいた戦争を持続するため、米政府はメディアにあやふや情報をリークした。駐ガボン米大使が「イラクがニジェールからウラン入手を図ったという情報は誤り」というと、リビー副大統領首席補佐官が大使の妻はCIA工作員だと記者に漏らし、大使の告発を貶めようとした。この件で情報源秘匿を貫いた記者は、実は開戦前、ホワイトハウスやCIAの見方に沿う大量破壊兵器の疑惑記事を何本も書いていたと。米政府高官でもCIAでも、本気になったら、ジャーナリズムは引っかからざるをえないのでは?
手嶋 そうだと思いますよ。
田原 NHKだって、本気で狙われたら引っかかるでしょう?
手嶋 僕は、ワシントンにいるとき、そういうことは日々さまざまなかたちでありうると思っていました。
佐藤 ただ、先ほど二つめの話を大嘘だといい、一つめの話を後回しにしたのは、私は本気になって引っかけようとしたのではないと見ているから。事態はもっと深刻で、大量破壊兵器の問題は、情報のキャッチボールから狂いがでてきたと思うんです。
田原 どういうこと?
佐藤 アメリカが最初からとった情報ならば、アメリカ人は病的に実証的なところがあるのでダブル、トリプルと裏を取って、結構しっかりしている。しかし、フセインのウラン入手の情報のそもそもはイタリアの情報機関。そのイタリアがイギリスをへて、アメリカと情報のキャッチボールをした。その情報の流れを知って、私は危ないと思った。
手嶋 その点、かつてのイギリスは、中東情勢に精通した人材を数多く擁していました。イギリスとソ連の二重スパイで有名なキム・フィルビーのお父さん――この人は中東で権威で、このJ・フィルビーは中東を手がける俊英を数多く送り出しています。そうした人材が中東各地に散らばって部厚い情報源となった。長期的なインテリジェンス戦略を、長年積み重ねてきた。アメリカは、ヒューミントの分野で大きく遅れを取っている。
佐藤 インテリジェンスや情報力とは、自分の弱いところをできるだけ隠して、強いところを実力以上に強く見せる技法なんです。軍事力が強い国に情報力が育ちにくいのは、最終的に何でも軍事力で解決できてしまうから。その場合の情報の有無は、解決にかかるコストがどの程度かという違いにすぎない。ところがイスラエルのような小さな国が情報の判断を誤ったら、それこそ国家がなくなってしまう。だから情報にものすごく敏感になり、情報の力を真剣に育て、慎重に判断していくことになる。アメリカが、ソ連と張り合っていた時代と違って世界唯一の超大国であるという無意識の驕りは、その情報の力を弱めてしまう。それが情報のキャッチボールのなかで、最悪シナリオを考えるから、狂いを生じてしまう。同じようなことが今後も起こると思いますよ。
田原 なるほど。
手嶋 「軍事大国はインテリジェンス小国になりがちだ」という指摘はその通りです。日本は軍事大国とはいえませんから、潜在的にはインテリジェンス強国になりうる素質を秘めている。インテリジェンスの「約束された地」(プロミスランド)なのかもしれません。そこで、『ウルトラ・ダラー』の舞台としたわけです。TOKYOはおもしろい場所なんです。
佐藤 そうそう。そうでなければ各国の情報機関は、現在やっているようなムダなことはしない。どこかの情報機関が40歳代半ばのヤツを一人東京に送り込むときは、家でパーティをやらなければならないでしょ。だから住宅は一等地で、家賃が月に120万から200万のところに入れますよ。車もそれなりのよいものを持たせる。一人置くのに年間5000万円くらいはかかるでしょう。
手嶋 ワシントンで僕は、機微に触れる情報収集は、全部、自前でやってました。BBCはフリンジ・ベネフィット、つまり経費は出してくれるんですが、NHKは出しません。パーティができる家の家具、内装、果てはカーテンからワイン、食事にいたるまで、すべて自前です。
田原 じゃあ、借金が相当たまったんじゃない?
手嶋 借金はしませんでしたが、蓄えはずいぶんと使い果たしました。家族には相当に負担をかけましたね。もっとも、インテリジェンスをめぐる情報源を危険にさらすようなことまでして、経費の請求などすべきではありませんが。ニュースソースに関わることだから、これ以上は申し上げられませんけれども(笑)。話を東京に戻すと、まあ各国いろいろな人が集まっている。意外に頑張っているところではバチカン市国。あのインテリジェンス能力はすごいですね。
佐藤 バチカンは怖いですよ。モスクワでもすごい仕事をしていますし。
田原 そうか。お坊さんのところは実はすごいんだ、情報力が。
佐藤 お坊さんのところは、非常に情報がありますよ。
田原 つまりは、東京はスパイ天国であると。それに気づかない世界第二の経済大国である日本は、軍事小国にしてインテリジェンス小国だと、こういう話ですね。
権力とはガセネタを流し、引っかけるものである
田原 また違う質問なんですが、佐藤さんや鈴木宗男さんをマスコミが総攻撃しました。佐藤さん、あれはなんだと思いますか?
佐藤 マスコミにはそれなりの根拠があったんでしょう。そういう情報を流した人がいたからですよ。
田原 検察情報で叩いたということ?
佐藤 いや、検察に流した人がいる。それは外務省です。外務省が情報を提供し、検察は警察や国家機関は嘘をつかないと思っているから、そんな悪い話が聞こえてくるなら事実だろうと思ってやった。ある意味で検察も被害者だと思いますよ。外務省に掃除をさせられた。
手嶋 その一方で検察に対して、条約や協定の解釈をめぐって、まっとうな供述をしていた人もいたんですけれど、検察は耳を傾けなかった。検察は、こと点で筋をはずしてしまった。公判を維持するために、いま、ずいぶんと苦しんでいるはずです。
佐藤 だって、事件を作りたいんですから。悪い話ばかり聞くに決まっています。
田原 検察は「国策捜査」で事件を作りたかった。では、マスコミが外務省のインチキ情報に引っかかり、それをワーッとばらまいたのはなぜ?
手嶋 焼き畑農業を続けすぎ、自分で情報の真贋を判定し、裏を取ることを怠った。オーソリティがなにか言ったというのは、記事にするのがすごく簡単ですから。僕は、検察担当の非常に優れた記者を幾人か知っています。しかし、やはり「検察の」というクレジットでしか仕事ができない人たちという側面があって、僕は違和感がありますね。
田原 記者にとっては、検察や警察が唯一の情報源。それとケンカしたら何も入ってこないでしょう。
手嶋 それはしかし、本来ならば検察や警察を主要な情報源としながら、同時に自らが調べ、裏を取り、調査報道をしなければならない。その部分が極端に弱い。
佐藤 官が積極的に嘘をつくことはないというのが、日本の文化だったからなんでしょう。
手嶋 でも、実は『ニューヨークタイムズ』でも同じ。ボブ・ウッドワードはかつては輝けるスター記者でしたが、『ブッシュの戦争』なんて何十万部のベストセラーになったのですが、いまでは誰も読む人はいないはずです。ブッシュ政権のリークだけで書かれているような本ですから。
田原 私は読んだけど、あれは紙くず以下ですか(笑)。
手嶋 だって、本に書かれたことに、いくつか間違いがある、といった類の話ではありません。カール・ローヴ(大統領上席顧問)などというメディアを操る魔術師がいて、「例のボブ・ウッドワードがチームを率いて、ブッシュ大統領がイラク戦争に至る過程を取材することになった。いいか。こういう順番で取材を受ける。おまえはこれをこう言え。君はあれをああ言え。この問題はこうだったことにしよう」と口裏合わせて段取りを組み、最後は大統領がインタビューに応じて迫真の演技をした。以上をそのまま書いたわけだから、つまり騙されて書いた本なのです。厳密な検証など、かけらもない。
田原 ニクソン大統領の失脚に至るウォーターゲート事件(1972年)のときも同じで、ディープスロートと呼ばれた内部告発者の言うがままにやった。
手嶋 まったくそうです。権力とはまさにそういうものです。
佐藤 同感です。鈴木さんや私がやられたのは理由があった。嵐の時に水路の水がどんどん上がっていく。いずれ堤防のどこかが決壊して洪水になるのは明白だった。要するに外務官僚か鈴木宗男さんのいずれかが世論のバッシングの対象となることが頭のよい外務官僚には見えていた。私のところは本来、コンクリートも比較的しっかりした丈夫な場所だったんだけれど、ツルハシを持ってきてカンカンカンと叩いたヤツがいた。外務幹部の中にね。そこから決壊していったと思うんです。
政官の関係についてのルールが、外交においては存在しないんです。外交官は政治の力を借りないと仕事ができない。政治家はきちんとしたスタッフがいないから官僚の力を借りるしかない。たまたま私も鈴木さんも、ある意味ではヘンな人。二人とも強情だったから、飲み込みも飲み込まれもせず、しかも強固な関係を築いた。そのやり方はダメだというルールはどこにもないが、ある時点からつぶせという話になった。
田原 ヘンな人って、どういう意味?
佐藤 たとえば、取り調べの検事がこういった。「鈴木さんとあんたほどの関係があるならば、普通は1億だって2億だって(外務省関連国際機関の)支援委員会から抜いているはずだ。しかし、カネの話が出てこないんだ。これがわれわれにとっては意外で、大きく見誤った。政治家と官僚のこの種の関係は、絶対カネと女が出てくる。どうしても出てこない」と。だから検察は、最初は佐藤と鈴木はホモじゃないかと調べたわけですよ。
田原 えっ、そうなの !? それは知らなかった(笑)。
佐藤 検察は、外務省の中からそういう情報が来たという。1993年12月にモスクワへ選挙監視に行ったとき、夜通し流れる選挙速報を訳してくれと鈴木さんがいった。私がホテルの部屋に行ったら、鈴木さんはエキストラベッドを入れてくれた。だからホモじゃないかというヤツが外務省にいるんです。私が「ホモなら備え付けの大きなベッドに一緒に寝ればいいだろう。エキストラベッドなんて必要ない」といったら、検察官は納得して「そうだよな。それにしても外務省はひどい組織だな。そんな話が聞こえてくれば、こっちは全部調べなくちゃならないんだ」とぼやいていました。
佐藤ラスプーチン事件の発端はチェチェン問題
手嶋 冒頭、田原さんが言われたように、日本の対ロ外交というのは、あきらかにいま暗礁に乗り上げてしまっています。私は外交ジャーナリストですから、言っておかなければなりません。今日の事態には、佐藤さん、そうここはラスプーチンというべきか、かなり重い責任がある。これだけ志も能力もある人が、どこでどう間違ってしまったのか。僕は同じ道産子同士だし、鈴木宗男さんのよい面も知っているつもりです。が、対ロ外交で鈴木さんとだけ組んでいいものだったのか。佐藤さんが本当に組むべき相手はもっと本格的なプレーヤーではなかったか。そうでなければ舞台は回らなかったはずです。事件の淵源はチェチェン問題の処理にあったのです。当時、僕は、佐藤さんとは本質的な意味で対立関係にあった。そのときの状況を検証しておきましょう。佐藤さん、まず読者にチェチェン問題を説明してください。
佐藤 チェチェン問題はというのは1999年まで、チェチェン独立派対モスクワの対立だった。しかし98年頃から、アルカイダが相当チェチェンに入ってくる。するとチェチェン独立派は、モスクワも嫌いだがアルカイダに席巻されたら民族独立なんかできなくないということで、モスクワと手を組むようになる。イスラム勢力側は隣のダゲスタンにイスラム原理主義国家を作り、いよいよ大運動に盛り上がりそうになって、モスクワは断固これを平定する状況になった。当時プーチンはロシア首相で、ロシアの情報機関も軍も「国際テロリズムが存在する。これは国境を越えたネットワークで、イスラムの帝国を作ろうとする本格的な武装原理主義運動だ」と主張する。これに対してアメリカやイギリスは「嘘だ。そんなものは存在しない。ロシアの人権弾圧や民族自決の抑圧の口実にすぎない」といい、ロシアと西側が対立したんです。
手嶋 さて、日本はどうするか。
佐藤 もっとハッキリいうと、当時外務大臣だった河野洋平さんがどうするかということですね。河野さんはハト派・人権派だし、外務省でイスラム研究会を作ったように、イスラム諸国との関係を重視していた。英米は、少しエリツィンが弱ってきたと思ったらプーチンというのが出てきたが、これは秘密警察出身でタチの悪いヤツだ、ここらでロシアのやりすぎを牽制しておこうという考え。そこで河野さんの意向も忖度し、外務省幹部がG8の外相会議ではG7で団結してロシアを絞めてやろうということになった。外務大臣も外務省もその方向でいこう……。
手嶋 という最終的な結論が外務省の中で出て、自民党の外交部会に持っていった。そこで鈴木宗男さんと最初に激突し、「鈴木宗男さん+佐藤ラスプーチン」と、ロシアを絞めあげようじゃないかという見解を固めた外務省の首脳陣との間で戦争に突入したわけです。
田原 ここが原点ですね。
手嶋 ここが問題なんです。当時の外務省の首脳陣は、ひとたびチェチェンをめぐる政策的見解を決めたのですから、鈴木さんと佐藤さんがどんなに圧力をかけようが、それを断固守るべきだったと僕は思います。しかし、みっともないことに、二人の威圧の前に膝を屈してしまったのです。ひとたびそれをやってしまえば、言うなりです。僕はそれを厳しく批判しているんです。ただ一人を除いて全員が、鈴木さんと佐藤さんの軍門に降ってしまった。土下座はしないまでも、深々と頭を下げて……。
佐藤 いや、社会通念上は明らかに「土下座」です(笑)。
手嶋 そのとき一人寝返らずに残った人がいた。その人は佐藤さんと鈴木さんにとっては天敵ですが、見所がある。僕が、佐藤さんが見立てを間違ったというのは、対ロ外交を打開するときは、まさにそういう人たちと連携すべきだったのです。
鈴木宗男と佐藤優の、外務省における力の源泉は?
佐藤 そこは認識が違うんだな。なぜかというと、私は外務省のレベルを超えるもっと上から、つまり内閣総理大臣から直に「鈴木さんとやれ」と言われていたわけですから。
田原 それは、いつの話?
佐藤 小渕内閣の時です。
田原 小渕さんが「佐藤は鈴木宗男と組め」と、確かに命じたんですか?
佐藤 小渕恵三首相と森喜朗さんから、明示的に言われていました。より正確に言うと、当時の外務省幹部が小渕さんか鈴木さんに私を差し出したんです。小渕さんには官邸に呼ばれて「おまえはちゃんと動いて、俺に報告に来い。俺がいないときは鈴木宗男のところに行け。とにかく鈴木とちゃんとやれ」と、当時の外務省事務次官と欧州局長と国際情報局長と官房長と総理秘書官の前で「それがおまえの仕事だ」と言われた。
田原 じゃ、ぜんぜんホモではないわけだ(一同爆笑)。
手嶋 これは、佐藤ラスプーチン事件の淵源を考えるときに非常に重要なところです。チェチェン問題で、外務省の首脳陣と鈴木・ラスプーチン組に対立が起きたとき、東郷和彦欧亜局長がこの混乱を助長してしまったのです。ロシア政府に辛口の見解を自分も一緒にまとめておきながら、対立が起きると右往左往して両者の調整を放棄してしまった。鈴木・ラスプーチンと極めて近いにもかかわらず。このことからも、明らかなように、対ロ外交の大きな方針は、外務省側が決めているのです。小渕首相の意向は確かに重要なファクターではありますが、実態として主導権は外務賞の側にあった。したがって、総理から言われても、外交のプロと連携しない限りは、外交の舵取りに影響力を与えることはできません。とりわけ、条約が絡んだ局面では、条約官僚との連携なくして事態は動きません。佐藤さんが正しく見立てているように、竹島の問題がまさにそうなのです。これほどの眼力を持ったひとも、自分のことがからむと見立てが歪んでくる。惜しむべし、ラスプーチン。
佐藤 いや、その認識は間違えていると思います。それは民主主義の否定になります。官僚は選挙によって民意の洗礼を受けていないのですから、あくまでも政治指導部に従うべきです。
田原 内閣を構成する閣僚をトップとする組織に属する官僚が、国会が選んで行政府を統括する内閣総理大臣に従うのは当然だ。それが民主主義だということね。
手嶋 いやいや、その浮かび上がった過程で、佐藤さんが本当の意味での同盟を組むべき相手は、当時から外務省内にいた。そこの見立てを誤ったということを僕はいいたいのです。島が帰ってきて、戦後体制の清算がかかっているのですから。
佐藤 手嶋さんのおっしゃることはよくわかります。確かに外務省で生き残るという観点から、私は見立てを誤ったと思います。しかし、私はあのとき政治指導部に軸足を置いたことは国益の観点から正しかったと今も思っています。少し話を戻せば、あのときは青天の霹靂で、鈴木宗男さんから電話がかかってきました。鈴木さんは「チェチェンはロシアの国内問題だという従来の方針を変更し、これは人権問題だとロシアに圧力を加えたらどうなるか。第一に、その見方は国際情勢の分析として正しいか。第二に北方領土問題にどんな影響を与えるか」と、二つの質問をした。
私は、一点目は「その分析は間違いです。ロシアのいう国際テロリズムは存在する。ロシアがタメにしている話ではない。イスラエルから聞いている話とも符合しており、イスラムのハンバル法学派に属するワッハーブ過激派、サウジのオサマ・ビンラディンたちのネットワークが世界で何かをやらかそうとしており、間違いなくダゲスタンとチェチェンをその拠点に据えようとしている」と答えた。二点目は「チェチェンはロシアにとって死活的に重要だから、チェチェンで人権弾圧だとロシアを絞めたたら、北方領土交渉は止まります」と答えた。
すると15分ほどして東郷和彦さんから電話がかかってきた。「君は鈴木さんに何を話したんだ」「これこれの二つです」「実は、あんたの意見は聞かなかったが、うちの役所でこう決めちゃって、いま鈴木さんとモメてるんだ」「そんなことを言われたって仕方がない。私は分析専門家として、正確な見立てを説明しただけです」。そのあと何を言ってきたかといえば、外務省の幹部たちから「鈴木さんが横になっちゃった。縦にできるのはおまえしかいないから、なんでもいいからやってくれ」と言われたわけなんです。もし、あのとき事前に外務省が一つの方針を決めたということを私が知っていたならば、恐らく私は自分の見立てをそのまま鈴木さんに伝えることはなかったと思います。
手嶋 そこが当時の外務省のだめなところでした。この混乱が日本の対ロ外交を迷走させていくひとつのきっかけになったのです。
田原 「鈴木宗男さん+佐藤ラスプーチン」の反対側にいた外務省幹部たちが、ある時点からドッとこっち側に来たと。ロシアを絞めるシナリオに反対されて?
手嶋 鈴木宗男さんという人と、佐藤ラスプーチンの風圧に押されてね。やはり外務官僚の自己保身だと思います。
田原 どういう風圧? 鈴木さんが怒鳴った? まさか殴りはしないね。
手嶋 だからいじめられて。これ以上楯突くと、自分の将来がない。
田原 たった二人で全員をいじめるわけ?
手嶋 そうだったと思いますよ。
田原 どうやっていじめるんですか?
佐藤 たいしていじめなかったですよ(笑)。鈴木さんは、このことで日ロ関係が停滞すれば全責任を取るんだなと、幹部たち一人一人に聞いたんです。私は、どうぞ全責任を取られたらいいんじゃないですかといった。
田原 なんで鈴木さんは、外務省でそんな力を持っていたのか?
手嶋 佐藤ラスプーチンがいたからです。やはりインテリジェンスの力だと思います。
佐藤 私は、そんなに力があるなんて認識は、持っていなかったんです。
田原 いや、持っていたんでしょう。みんな怖がっていた。
佐藤 そこが私の一番のズレなんです。私は鈴木さんがぜんぜん怖くなかった。だから、ほかの人も鈴木さんを怖がっていないと思っていたんです。それが私には見えなかったんです。
田原 クレムリンの深奥に詳しい佐藤優が、外務省の幹部連の気持ちはわからなかった。それで足下をすくわれてしまった……。ものすごく有能なスパイが女房や息子の気持ちがわからないというのは、ありそうな話だな。インテリジェンスの力とは、そういうものか。
佐藤 外務官僚は鈴木さんに対してであれ、小渕さんか野中(広務)さんに対してであれ、国益上必要ならば対立を恐れずに自らの意見を述べる「官僚道」をわきまえていると思っていたからです。ただ一つ重要なポイントは、手嶋さんが一人寝返らず頑張っていたといったのは誰かと聞かれましたが、これが谷内正太郎さんだった。私は鈴木さんに「谷内のところに行って、俺の考えを伝えてこい」といわれて、そうした。すると谷内さんはこう言ったんです。「私は鈴木さんには詫びない。鈴木さんの考え方は、外交論として一つの筋の通った考え方だ。それを踏まえたうえで外務省の方針を決める。それで鈴木宗男さんとぶつかるならば、仕方がない」と。
田原 それは立派だ。
佐藤 それを、私は鈴木さんに伝えた。鈴木さんはなんと言ったか。「谷内はしっかり者だ」と、こういう話です。
田原 彼は断じて土下座なんかしなかった。
佐藤 しないよ。しないしない。土下座する人がおかしいんですよ。
なぜ日本外務省の対中外交は腰砕けか?
田原 ちょっと中国問題で質問。佐藤さんはある対談で、日本は中国に対して腰砕け外交をしているという。靖国へ行き続ける小泉さんは、中国に対して相当強気になっていると見えるが、なぜ腰砕けなんですか?
佐藤 外交というのは「薄っぺらい論理」が重要だと思うのです。たとえば2005年春に北京の日本大使館や上海の総領事館が民衆に襲撃された。これは、大使館に石を投げたヤツは国際法違反で悪いと、それだけの薄っぺらい論理でいい。2004年5月の上海総領事館の館員自殺事件も、中国の公権力がウイーン条約に違反知るどんなアプローチを仕掛けてきたかという薄っぺらい論理でいい、そこに、歴史問題などをからめると複雑になりすぎる。だから、薄っぺらい論理で土俵を制限し、勝てる状況を作って対応すればよいのに、日本外交は何もしない。
田原 なるほど。大使館のガラスが何枚割れた、ペンキの清掃代はこれこれだと請求書を示して、「あんたのところの警備の不備だ、犯人を捜してくれ」とだけ、下世話にいえばいいわけだ。歴史問題を持ち出してくれば、「何? 未解決の歴史問題を解決するのに、民衆の投石を容認するって、それが先進国のいうことですか?」といえばいい。
佐藤 そうです。上海の総領事館員が、2年前に中国の当局から脅迫され自殺したならば、これは官邸に報告して然るべきです。
田原 なんで報告しないんだろう?
佐藤 ですから腰が砕けているわけです。中国と事を構えるのがイヤなの。ネガティブなことで中国と外交交渉をしたくない。
田原 なんで外務省は中国にそんなに弱みを持っている?
佐藤 仕事と私生活の双方で中国に対する「借り」が大きくなっているからでしょう。それに弱みを握られているヤツが外務省幹部にいるんでしょうね。
田原 手嶋さん、どうですか?
手嶋 象徴的な例を申し上げましょう。日本の安全保障体制は、二つの有事を想定した安全保障の盟約です。二つの有事とは、朝鮮半島の有事と台湾海峡の有事です。しかしながら、中国政府は、当然認めようとしません。なぜならば、台湾は中国と密接不可分な領土であり、日本はポツダム宣言で台湾の領有権を放棄したはずだ。だから、日米安保体制の想定するいわゆる極東の範囲に含めれるはずはないと。この中国の主張に沿った見解を取ってきたのが、日本外務省のなかのチャイナスクールと呼ばれる人たちです。実際、日米ガイドラインの見直しが議論されたとき、この外務省が抱える矛盾がはしなくも露呈してしまったのです。詳しいいきさつは省きますが、極東の範囲をめぐる答弁で、有力次官候補だった高野紀元北米局長の首が飛んでいます。
佐藤 あれだって、当時の竹内行夫条約局長が煽ったわけですからね。高野さんはそのツケを払わされた。
手嶋 竹内条約局長も当事者の一人でした。安全保障という大事なことでも中国ときちんと対応できないのですから、上海の総領事館の話ではなおさらです。
佐藤 もっと根本的な問題がある。いまの外交官たちは論理能力が弱くなっている。理詰めで物事を詰めていくことができなくなっている。
靖国問題でも「薄っぺらい議論」を展開せよ
田原 最後に、あえて下世話なことを聞きます。靖国神社に小泉純一郎首相が参拝するのは、どう考えますか?
佐藤 私は行けばいいと思う。
田原 行くと、日中首脳会議ができない。
佐藤 どうぞと。中国が首脳会談をやりたくないんなら、いつまでもやらない。それで構わない。
田原 靖国はポスト小泉にも影響してくる問題で、マスコミがポスト小泉の最大の問題として扱うのは、靖国問題ですよ。私は最大じゃないと思っているけどね。
手嶋 日本外交は、靖国へ小泉総理が行ったことによって、あらゆる意味で隘路に立ち至りました。この結果責任は、小泉政府が取らなければいけません。そして、経緯はともかく負の遺産のもとに次の総理が出てくるのですから、新しいリーダーは然るべき打開を図らなければ。といって、中国の言いなりにやれとは言いません。
佐藤 田原さん、正確に理解してほしいんですけど、私はいたずらに対中強硬論を唱えているわけではないんです。これも外交では「薄っぺらい論理」が必要だという話です。どういうことかというと、日本は主権国家であり、民主主義国である。その日本で、小泉さんが「靖国へ行きますよ」と、総裁選その他で公約として言った。その人が民主的手続きによる総選挙2回と参議院選挙1回によって、国民の支持を得ている。すると日本が民主的な主権国家だということを前提とすれば、総理大臣が公約を履行することには、なんの問題もない。それを変えたいならば、日本の政権を変えなくてはならない。だから、これは譲れない国民国家の原理原則ですよと、言わなければならない。
たとえば北朝鮮は、金正日の誕生日に白いナマコが出てきて祝福したとかなんとか宣伝しているわけです。そんなバカなと日本政府がいうのは余計なお世話で、放っておくしかないでしょう。中国は歴史問題でも靖国でも、いくらでもいちゃもんをつけて議論できるが、主権国家の日本がいちいち聞く必要はないんです。それをほったらかして首脳会談ができなくても、日中はお互いに他を必要としているんだから、一定の期間がたてば中国のなかで対日関係をどうするかという競争が必ず始まる。その状況のなかで首脳会談を開くことができるような環境を整えていけばよい。
田原 小泉さんは、確信があって靖国へ行っているわけではないね。最初は遺族会に行くと言ったから行った。2回目はなんとなく行った。すると中国が大反対というから、その外圧に屈することは日本国総理大臣のプライドが許さない。だから行く。意地ですよ。
佐藤 いや、個人的な意地としてとらえないほうがいいと思う。そのような中国に対するイラ立ちが日本人の集合的無意識の中にある。小泉さんは天才的な能力でそれをつかんだから行ったんです。中国にコケにされているというような意識を持っている日本人が多いから、それに乗ったほうがいいという判断、勘でしょう。いずれにせよ、中国には薄っぺらい論理で対すればいいと思う。
田原 ポスト小泉は、どうすべき?
佐藤 それはぜんぜん別の話。ポスト小泉になる人が自分で判断すればいい。
田原 だから教えてやってよ、ポスト小泉に。
佐藤 いや、私はそこはずるいんです。ニュートラルなの。どっちでも組み立てられるのが外交専門家の仕事。
田原 そうか。行かないなら行かない論理が作れる。行くなら行く論理が作れる。
佐藤 それは政治だから、あなたが決めてください。行く行かないに私は基本的に関心がありません、と。私個人についていえば、クリスチャンの私は、靖国神社に私が信じる神様がいるとは思わない。しかし、ナショナルなことにはそれなりの思いがあるから、靖国神社に対して無礼なことはしないし、シンパシーもあります。だから私自身も定期的に靖国神社を訪れ、英霊に感謝している。
田原 靖国神社にA級戦犯が合祀されている問題については?
佐藤 中国がそれを問題視するという理屈はわかる。一方、宗教法人・靖国神社の側にいったん合祀した神様は分祀できないという理屈があるのもわかる。理屈の真理はいくつもあって、それぞれ同格でしょう。そのなかでどうやって折り合いをつけるかは……。
田原 官僚は判断しない。政治家が判断する。
佐藤 そう。だからテクノクラートが言うべきことは、「靖国神社に行ったらメチャクチャなことになりますよ。しかし、それでも行かれるならば、その上で対中外交を組み立てなければならないですね」と、一言でいえばそういうことです。そして、時の総理をお支えするために、官僚としての全能力を投入する。それだけのことです。
日中は小泉8月15日参拝で徹底的に衝突すべきだ
手嶋 現在の中国が続ける「愚か」というべき外交が、さらに問題を混迷させています。次の総理が靖国神社に行かなければ首脳会談に応じてやる、と中国はいう。「日中首脳会談」の「値段」は、そんなに高くない。外交面での小泉総理のおそらく唯一の功績というべきか、「日本国首相の靖国参拝」の外交上の「値段」は、小泉さんの行動によって、ほとんど天井まで高騰した。そのカードを使って小泉さんが後世に名を残そうとすれば、中国が日本の安保理常任理事国入りを明示的に認めるくらいの価値はあると思いますよ。ところが中国は、首脳会談に応じてやると安値をつけてる。これでは、首相の靖国神社の参拝に反対し、やや中国寄りの、中国の論理も理解できるとする人たちすら、敵に回すことになってしまう。
佐藤 おっしゃる通りです。靖国神社をめぐる論争とか、死者の魂をめぐる論争というのは、シンボルをめぐる闘争です。人間の表象能力によって、それはいくらでもエスカレートさせることができるんです。こういうものを日中関係からできるだけ外すためには、一度徹底的にぶつかってみればいい。
田原 どうやるの?
佐藤 つまり、小泉さんは2006年8月15日に、靖国神社に行くんですよ。
田原 うん。私は行くと思います。
佐藤 それで、中国が徹底的に反発するならどうぞと。
田原 同友会をはじめ財界の反対はどうです? 小泉さんは、あんたら商売の論理だろ、商売のために政治が頭を下げることはないよ、というんだけど。
手嶋 アメリカと日本が台湾海峡においてイージス艦で行動を共にすれば、中国は、それを座視しないでしょう。中国にある日本の工場全部を血祭りに上げることはないにせよ、トヨタの中国工場を凍結するくらいのことはありえましょう。それは商売の論理の範囲をはるかに超え、政治の領域の話です。その意味では、小泉総理が政治の論理が勝っているというのは当たっています。ただ、小泉総理が外から見えるほどは強気ではないのは、田原さんご自身が一番知っているのではありませんか?
田原 まあ、その話はいいや。
手嶋 一つだけご忠告します。官邸や公邸の電話で、首相と重要な問題について話してはいけませんよ。外国のインテリジェンス機関が聞いていると、思われたほうがよろしい。
佐藤 そうそう。何しろ田原さんは「権力党」の幹部なのでね。中国問題で気をつけなければいけないのは、中国側のナショナリズムや思想史に関する学術的研究のレベルが非常にお粗末だということです。とくにヨーロッパのナショナリズムなどの基礎研究の底が浅い。自分たちのやることによって、足下の中国で何が起きるか、日本ではどうかという見通しが悪いと思います。この点、日本のアカデミズムや民間には優れた知的集積があります。これを外交に生かすのもインテリジェンスの任務です。もう一つ、中国問題で参考になるのは、インテリジェンスの世界の定石ですが、行き詰まったら戦線を広げることですよ。たとえば中央アジアや新疆ウイグルを安定させるための日中協力をやるとかね。
田原 将棋でも、劣勢のときは戦線を広げろといいますね。こじ開けられた場所は放っておいて、思いがけない手をいろいろ指してみろと。
佐藤 深刻なのは、役者がいないことです。ズバリ問題をいえば、外務省事務方のナンバー・ツーの政務担当外務審議官ですよ。これがまったく機能していない。これがすべての汚れ役となって、総理や外務大臣が活躍できる環境を作らなければいけない。できるできないじゃない、脅してでもやらせなければならない。谷内さんの悪口をずっと言い続けている外務省幹部がいるんですが、その人物が言ったことが30分もたたないうちに、電話で私に伝わってくる。もちろん外務省関係者からです。どうも、外務省のモラルの崩壊は異常ですよ。
手嶋 自らの栄達や保身を越えて、本当のリスクを取る外交官が、どれほどいて、どのようにリスクを取るのか。
佐藤 外務省の構造的な問題として、課長レベルの連中が語学も弱く、サブスタンス(外交の実質的内容に関する知識)交渉力も弱い状況になっている。ようするに、外務省の骨格自体が弱くなっている。だから5年後10年後が、私は本当に心配なんです。現実的に考えれば、40歳未満の課長補佐以下のキャリア職員と、年齢に関係なく優れたノンキャリア職員を今から鍛えるしかない。
田原 日本外交、そして外務省の本当の姿が、よくわかった。長時間、ありがとうございました。
(この鼎談は2006年5月29日に行いました)
「オフレコ!」vol3(平成18年8月3日発売号)