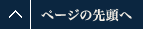「危機の指導者 第1回 中台危機 李登輝が放ったスパイ」
プロローグ
シェラトン・ホテル・タイペイの電話が鳴ったのは夜もまだ明けきらない時刻だった。 「李登輝前総統弁公室ですが、このような時間に恐縮です。会見は午前十時からとお伝えしていましたが、日程を急ぎ変えていただきたいのですが―」 要人の会見は、直前になってキャンセルされることがしばしばある。こんどもやはり―と覚悟を決めかけた。
「総統が早々と起きて、あなたをお待ちです。まことに申し訳ないのですが、すぐに車を拾って大渓鎮のお宅に向かっていただきたい」
李登輝前総統は、未明から起きだして、インタビューにどう応じたものか、あれこれ考えを巡らしているらしい。いますぐにも話し始めたい様子だという。秘書もすぐに自宅を飛び出すが、間に合いそうもない。とにかく一足早く大渓鎮の私邸に向かってほしいと慌てている。 台湾海峡に風波を巻き起こした九六年の危機とは、この国を率いた政治指導者にとって、それほどにずっしりと重いテーマなのだろう。いまこそ機密の封印を引きちぎって、あの危機の日々を語りつくそうとする李登輝の気構えが伝わってきた。
「大渓鎮の前総統邸へ。全速力で―」
台北の市街を大急ぎで抜けて郊外の桃園県を目指した。
それは異例尽くめの会見のはじまりだった。李登輝邸に通じるゲートを二つくぐり抜けると、通用門にたつ警備員が無言で頷き通してくれた。
鮮やかな黄色い花びらの真ん中を濃い紅色に染めた波斯菊が邸の周囲に咲き乱れていた。その傍らには桔梗が紫のいろどりを添えていた。台北市内の喧騒から逃れて、空気が清々しかった。玄関には、一八一センチの威丈夫がひとり、背筋をすっくと伸ばして立っていた。
かつて司馬遼太郎は「山から伐りだしたばかりの大木に粗っぽく目鼻を彫ったようで、笑顔になると、木の香りがにおい立つようである」と描写した。そのひとがそこにいた。一介の牧師となって山地に福音を伝えにゆきたいと、引退後の夢を語って、ここに終の棲家を定めたのだった。
夜もまだ明けないうちから起きだして客人の来訪を急かしたとは思えない、そんな悠々とした雰囲気があたりを支配している。邸内に一歩足を踏み入れると、ことごとくが書物で溢れかえる部屋だった。周囲の壁が万巻の蔵書で天井まで埋め尽くされている。
居間は広々としているが、いたって簡素だった。李登輝は、隣り合った席を勧めてくれた。そしてガラスのテーブルに置いてあった秘の印が捺した数冊の書類を少しだけ前に押し出した。 「これを外に差しあげるのは初めてじゃないかな。一冊のノンフィクションが書けるかも知れませんよ。まあ、あとでゆっくりと説明しましょう」
私は深々と礼をして、持ってきた近著『ウルトラ・ダラー』を贈呈した。
「そうそう、『ウルトラ・ダラー』ね。この小説で私はどういう役目をさせられているの。何ページかな」
「三百十三ページに記述があります」
「ああ、台湾の李登輝グループの基本戦略か―」
「高遠希恵という女性の官房副長官が、BBCの東京特派員にして、英国秘密諜報部員スティーブン・ブラッドレーに、緊迫する台湾情勢を語り聞かせるくだりに総統は登場します。ここなのですが―スティーブン、あなた、李登輝に会ったことある。恐ろしいほど読みの深い政治家だわ―」
「女性の官房副長官か。面白そうだな。早速、妻にも読ませようじゃないか。彼女は本を読まないと眠れないんだ。もう明け方の三時か四時までいつも本を読んでいる」
李登輝邸は、さながら小体な図書館だった。レーガン、ニクソン、トルーマン、サッチャーと各国の政治指導者たちを描いた著作を収めた書棚がある。その一冊に『指導者たち』を見つけた。著者のニクソンは、そのなかでシンガポールのリー・クアンユーを「小さな舞台の大きな俳優」として取りあげ、「もし違う時代に別の国家を委ねられていたら、きっとチャーチル、ディスレーリ、グラッドストーンのように名を残したものを」と記している。アジアの小国は中国系から優れた政治家を生み出してきた。李登輝もまさにそのひとりだった。
岩波文庫がびっしりと並んでいる。その一冊、一冊には付箋が挟まれ、じっくりと読み込まれている。絶版となった岩波文庫も多く、大きな書店よりもよほど点数が揃っているという。
李登輝は深夜ひとり書物と向きあって、静謐の時を過ごし、それから眠りに就くという。そうした毎日は総統時代から少しも変わらないという。著者たちと日々の対話を交わし、思索を深めることで、政治家の内面を豊かなものにしてきたのだろう。
「私はひょっとしたら近く日本へ行きますよ。そのときには日本の人々に言いたいと思っている。国際金融資本が暴れまわっているいまこそ、道徳体系をしっかりと持ってほしいと。そうした国家だけが生き残る。そう、自分なりのスピリッツを持った人間がいる国、そうでなければいけない。一九九六年、あの危機の年にあって、まさにそう感じたんだ」
東アジアの特異な政治状況が生みだしたこの政客は、ちょうど十年前のあの日々に思いをめぐらして、問わず語りにかたりはじめた。
「九六年飛弾危機」
「解放軍の第二砲兵部隊は、中国大陸から四基の短距離ミサイル「東風」を相次いで発射しました。北の台北と南の高雄を標的に仕立てて、ミサイルは、ふたつの都市の上空を掠めるように飛び、それぞれ沖合に着弾しました」
「飛弾発射」の報は、李登輝総統に急報された。一九九六年三月八日、未明の出来事だった。
側近によると、軍からの一報に接した李登輝は、ほとんど表情を読ませなかったという。危機に際して、国家の指導者が慌てた様子を少しでも見せれば、政権が動揺していると外部に悟られてしまう。
中国の首脳部は、台湾史上初めて実施される総統の直接選挙にミサイルで揺さぶりをかけようとしている。南と北の大都市の沖合にミサイルを打ち込むことで台湾全島をすっぽり射程に収めていると無言のうちに示したのだった。続いて台湾全島を包囲するように、陸、海、空三軍の大がかりな上陸演習を予定している。
彼らの羽音に驚いて、戒厳令に追い込まれてしまえば、初の民主選挙の正当性が失われてしまう。中国側の狙いはまさにそこにある―。李登輝は、いまこそ沈着にと、自らに言い聞かせたという。
台湾の軍部にも軽々に動いてはならないと厳命した。そして一般の人々にも冷静に対処するように終始呼びかけたのだった。
陸海空の三軍合同演習は、いつ本格的な台湾侵攻に姿を変えるか、予断を許さない。だが李登輝は、中国側が台湾と戦火を交える意図はないと、正確に先行きを読みきっていた。三軍は、規模を当初よりかなり縮小して演習を終えている。
機密文書は語る
李登輝がテーブルに置いていた文書には「九六年両岸関係の回顧と展望」という表題が付されている。それは無機的な文体で、あの危機の日々を淡々と綴っていた。
それによれば、解放軍は、作戦の第一段階で台湾の政治・軍事の拠点をミサイルで攻撃を加える。第二段階で台湾海峡の制海、制空権を確保し、海峡を封鎖する。そして第三段階として、台湾本島に侵攻し、上陸を敢行するとしていた。
だが実際には、解放軍は、第一波のミサイル演習で四発を目標海域に撃ちこんだものの、第二波の海峡封鎖は最初の三日間だけで早々と取りやめてしまい、第三波の上陸作戦は小規模な掃海、上陸演習にとどめたと記している。
事態は李登輝の読みどおりに推移していったことをこの文書が確認している。
このひとは、六〇歳になろうという年まで、農業経済の地味な研究者だった。だが、わずか数年のうちに、政権内に揺るぎない人脈を築き、確かなインテリジェンスを吸いあげる態勢を整えて、沈着な行動の裏づけとしていたのである。
「総統府にはじめて入った頃、李登輝は、台湾人のくせになぜ総統なんぞになったのかね―そう人々は思ったはずだ。あとせいぜい、一、二年しかも持つまいとね。こうしたなかで、実権を徐々に掌握していったんだ。知らないふりをしながらね。勝負どころは、軍と情報機関の掌握だった」
中国大陸の情報は、安全局の所管であり、その諜報報告は総統に直接あがってくる。安全局こそ、全世界にさまざまな人間を配し、外交官より職員が多い情報収集の要だった。
「朝、総統府に出勤すると、まず諜報報告が届けられる。これらの報告を毎日読んでいると、うん、この件は、こうなったかと事情が呑みこめてくる。この連中たちは嘘をついているな、と判るようになるんだ。彼らは仕事がないと嘘をつく」
中南海の意中
李登輝が明らかにした内部文書は、台湾側が、中国共産党の中枢部から政策決定をめぐる重要情報を刻々と入手していた事実をはっきりと記している。
台湾海峡危機に際して、台湾当局が最高度のインテリジェンスを中南海から得ていたことを初めて裏付けた貴重なドキュメントである。
「当時、当方が優れていたのは、情報が迅速でかつ正確であったことだ。『付録の1』に見られるように、九六年以来の中国共産党が行った重要な政策決定に関する情報を当方はすべて蒐集していた。とりわけ、九六年三月の軍事演習に関わる中国共産党の情報を迅速に掌握していた。それが政策の決定に資するところが大きかった」
今回明らかにされた内部文書からは、文中にある「付録の1」は削除されている。中国共産党政治局から議事録を入手できる人物が送ってきた極秘の諜報レポートだからだろう。この報告には情報源を明かしてしまう箇所があったはずだ。情報源の身元を秘匿するため「付録の1」を非公表としたのだろう。 台湾の当局は、これらのインテリジェンスを通じて中国共産党の中枢の動きをほぼリアルタイムで把握していた。中国共産党は、三軍の合同演習を終えたわずか二日後の三月二十七日から二十九日まで、政治局会議と政治局拡大会議を招集した。その席上、中国共産党軍事委員会副主席のが「台湾に対する軍事演習の状況報告」を、また人民解放軍の副総参謀長、熊光楷が「わが軍演習の台湾政局における初歩的影響」と題して、それぞれ特別報告を行っている。
内部文書は、そうした政治局の模様を生々しく伝えている。
軍事委員会の副主席、張万年は、今回の軍事演習の成果を検討してみたが、五つの成果が認められたと、つぎのように述べている。
まず、第一に、台湾の独立勢力に重大な打撃を与えたことだと演習の成果を誇って見せている。
第二に、台湾問題に手を延ばそうとする日米の両勢力に厳重なる警告を与えたことである。とりわけ、アメリカに台湾の独立に反対する政策的立場を表明させたことに意義があると指摘した。
第三に李登輝らに中国の統一を目指すといわしめた。これは今後の両岸関係の発展と台湾政治に対して戦略的意義があると指摘し、軍事演習が統一に向けた機運を強めたと強気な解釈を披露している。 第四には、全国人民の愛国主義の熱情を引き起し、和平統一に重大で深遠な影響を与えたと型どおりの見解を示して見せた。
そして第五に、今回の演習で軍が鍛えられたと総括している。
ここで張万年が江沢民に「こんどの演習は気象条件がとても悪かった」と釈明した。すると江沢民は「気象条件が悪いからこそ、各部隊は鍛えられるものだ」と応じている。
台湾の情報当局は、江沢民の軍に対する掌握はいまだ不十分と分析していた。しかし、今度の軍事演習を機に、江沢民側が軍の首脳部に攻勢に転じようとする様子を活写して興味深い。
同時に政治局の拡大会議では、軍事演習をめぐって驚くほど率直な反省も表明されている。
「こんどの演習は、国際情勢と台湾情勢の双方に影響を与えはした。しかしながら、李登輝は非常な高得票で当選を果たしてしまった。演習の所期の目的は達せられなかったというべきだろう」
中国共産党の政治局は、台湾への軍事侵攻の意図は持っていなかった。その一方で、ミサイルによる脅しで、あわよくば李登輝を総統の座から逐うと考えていたことがよくわかる。
「演習の実施に際しては、関係の各部門の協力が必ずしもうまくいかなかった。このため、台湾に対する圧力を削ぐ結果となってしまった。とりわけ、外交部の対応には、改善の余地がある」
張万年はこう指摘して、外交部の対米外交を手厳しく批判した。アメリカ政府が空母を中核とする機動部隊を台湾海峡に差し向けようとは全く予想していなかったと不満を述べた。
「中国の外交当局者が演習の狙いをアメリカ側に明かしてしまったことで、台湾への圧力を大きく減じてしまった」
もし中国の外交当局者が、これほど早々と武力不行使の保証を与えなければ、米中の武力衝突を恐れて、クリントン政権は機動部隊の派遣を見合わせたかもしれない。そうなれば台湾は演習によってより動揺したはずだという口吻が読み取れる。
そうした一方で、中国側は、自らの軍事面の欠点を率直に認めている。
「解放軍には渡海作戦の能力が不足している。空軍は全天候下での作戦能力に改善の余地がある。空挺部隊をもつ緊急展開部隊の質と量を高めなければならない。さらにはミサイル発射に際しては、各軍の様々な連携が必要だ。さらに一歩進めて論じれば、長期戦に備える能力と後方支援の能力が不足していた。そのため第一師団の海、空軍部隊では、士気に悪影響を及ぼした」
さらに会議では、演習で多くの死傷事故が頻発した事実を挙げている。実際に百四人が死亡した。そうした事故のなかでも水陸両用車が転覆し合わせて三十人が即死した悲惨な事故が報告されている。
中国当局は、アメリカのクリントン政権が空母機動部隊を台湾沖に派遣すると考えていたのか―。九六年の台湾海峡危機でながく論争を呼んできたこの問いに、内部文書は「予想外の出来事だった」とはっきりと認めている。
人民解放軍の合同演習に先立って、ワシントンを訪れた外務次官劉華秋らが「台湾攻撃の意図なし」と漏らしたことで、李登輝政権に選挙をやすやすと実施させてしまったと指摘している。
一連のミサイル発射に台湾攻撃の企図なし。こうした極秘のインテリジェンスを北京と台北が共有し、双方が巧みな「京劇」を演じていたとする見方がある。だが、中国側はミサイルを台湾の民心に揺さぶりをかける手段に使っていたのであり、合同演習は、まさしく実弾を込めないもうひとつ戦いだった。その危うさを過少評価するわけにはいくまい。
李登輝が、情報機関を掌握する一方で、軍を完全に把握していなければ、これほどの危機を冷静に乗りきることはできなかったろう。学者出身の政治家のどこにそれほどの力が眠っていたのだろう。 それは、国民党大陸派を代表する実力派の軍人、郝柏村との戦いではじまっ た。
李登輝は、総統府に入ると、参謀総長だった郝柏村を国防部長から行政院長にと起用し、軍の実権から遠ざけようとした。細心を極めた人事の布石だった。だが、やがて両雄に対決のときが訪れる。郝柏村は、軍を完全に退き、行政院長となったあとも、軍の要職にある幹部らを国防部に定期的に集めて、軍事会議を主宰していた事実が判明する。参謀総長の人事権にもしばしば介入し、三軍の最高司令官としての総統の権限を侵している。隠れた軍の支配者を除かなければ―。ひとたび決断するや、李登輝の動きは素早かった。郝柏村から実権を奪い、軍の組織を掌握していった。軍を握らないまま、九六年を迎えていれば、危機の様相は違ったものになっていただろう。
中・台極秘チャネル
九六年のミサイル危機に際して李登輝の切り札となったインテリジェンス人脈。中台間にこうした地下水脈が生まれる端緒は李ファミリーにあった。
李登輝は、たったひとりの、だが若くしてガンで亡くした長男、李憲文の名を挙げた。長男といまも同居している嫁は、野にあったひとりの学者のもとに足しげく通っていた。一九八〇年代のことだった。台北市内に私塾のようなものを開いていた在野の学者が南懐瑾だった。
「うちの息子も嫁もみな、南懐瑾の弟子だったんだ。彼はなかなかな戦略家だったな。志のある若い者を集めて座禅を組んだり、儒学の読書会をやったりしておった。だが、当時、総統職にあった蒋経国は、南懐瑾だけは何としてもダメだと言ってきかない。ついに香港に追い払ってしまった」
蒋経国は、その鋭敏な政治的嗅覚で、この在野の学者に危険なものを感じとったのだろう。だが、彼の死後、総統職を引き継ぐ李登輝にとっては、南懐瑾の香港への追放は予期せぬ出会いを生み出すきっかけとなった。
わが子の家庭教師。それは政治家が有能な若者を抜擢し、人脈を造りあげる温床になるという。李登輝の場合がまさにそうだった。李登輝の側近、蘇志誠も、李憲文の家庭教師だった。この若者は、やがて総統府に入って秘書室主任を務めることになる。
「香港に去った南懐瑾は、私が総統になると、秘書の蘇志誠にいちど香港になないかと声をかけてきた。私が指示して行かせたわけじゃない。詳しいことなど、知らなかったんだよ」
やがてこの香港行きには、ひとりの女性も同行するようになる。同じ李登輝の人脈に連なる鄭淑敏だった。彼女も後に閣僚ポストである政務委員などを歴任し、中国テレビの会長を務めている。
南懐瑾は、彼らを迎えて、香港に中国の上層部につながる人脈を紹介していった。中国共産党の主席であり、人民解放軍の長老、楊尚昆の側近をはじめ、両岸関係のキーパーソンとして活躍する汪道涵や汪道涵をはじめ錚々たる顔ぶれが揃っていた。
「南懐瑾はどうやらはじめは私に金を出させようとしたらしい。中国大陸の鉄道建設の資金を台湾から引き出そうとした。ところが、このプロジェクトはうまくいかなかった。だが、このときにできた両岸関係は終わらなかった」
蒋経国の急逝で総統職を引き継いだ李登輝が、一九九〇年に再選された頃から、フィクサー的な存在だった南懐瑾のチャネルは、にわかに重きをなしていく。鄭淑敏はしばしば中国に出かけ、放送番組の売買を名目に人脈をさらに広げていった。こうして中国大陸に張り巡らされた人脈も太く揺るぎないものになっていった。
「はじめは密使でも何でもない。彼らにお金を出したこともない。みな進んで情報を持ってきた。先方とやり取りを記したメモを見せ、録音テープを聞かせてくれた。こうしたなかから江沢民の側近、中央弁公庁の主任だった曽慶紅も出てくるようになったわけだ。この曽慶紅が、私の側近だった蘇志誠と仲よくなった」
曽慶紅は、野中広務元自民党幹事長と太いパイプを持っていることでも知られている。日本や台湾の要人の懐に飛び込んで親交を結ぶ胆力を持ち合わせているのだろう。同時に、危険な前線に単身乗り組んでいくだけの信任を江沢民から取りつけていたのだろう。
こうして中国と台湾の両岸を結ぶブリッジが構築されていった。中台の「民間交流機関」が造られ、地下の水脈を介して、江沢民の台湾問題に関する「八項目提案」や李登輝の「六項目提案」は、事前に互いに通知されていたのである。
もうひとつの極秘情報源
「先方が撃ってきたミサイルはすべて空砲だった」 総裁選挙のさなかに漏らした李登輝のひとこと。この「空砲」発言は、中国当局を震撼させずにはおかなかった。
確かに人民解放軍は、ミサイル「東風」の弾頭に実弾をこめてはいなかった。代わりに四基のミサイルが目標海域に正確に着弾したかどうかを確かめる計測器を弾頭のなかにひそかに収めていたのである。 なぜ、李登輝は、この軍事機密を知っているのか。最高レベルの情報が台北に漏れている―。こうした疑念を北京に抱かせてしまった。そして、三年の後、犠牲者を生む端緒となる。 「私が握っていたのは、政治的な交渉のチャネルだけでなかった。先方の軍の方面についても、インテリジェンスを持っていたんだ。だから、先方のミサイル発射がなにを狙ったものなのか、総合的に判断することができた」
九六年当時、中国政治局の内部で江沢民はまだ十分な権威を確立しておらず、その地位もさほど安泰ではなかった。軍の首脳部に引きずられる状態にあったと台湾側は見ていた。そして、こうした見方を裏書するもうひとつの極秘情報源を握っていたのである。
「これまで培ってきた解放軍の情報を総合すれば、先方の軍は本気になってわれわれとと戦う気はない、これは心理的な押さえつけだと見立てたわけだ」
李登輝は、インテリジェンスを扱い慣れた政治家である。それだけに総統の座を降りたあとも、国家の安全保障にかかわるインテリジェンスの保全には慎重だった。とりわけ情報源の秘匿については自らに厳格なディシプリンを課してきたといっていい。その李登輝が思い切った発言をした。
「彼らの軍隊はね、われわれは知っているのだが、いわゆるスマグリング、つまり、物資の密輸をかなりやっているんだ。アモイのスマグリンがもっともひどい。こうした連中たちとは、スマグリンの取引を通じてある程度のかかわりがあるからね。」
このくだりには重要な情報が隠されている。人民解放軍がアモイなどで手を染めていた密輸取引を通じて、台湾側は中国の軍内部に情報源を培っていたことが窺われる。
こうして獲得した最大の獲物こそ人民解放軍後勤部の軍械部長だった。新鋭兵器の調達を担当する要職である。九六年の危機当時、この職にあったのが劉連昆だった。
早くから台湾側の極秘エージェントとなっていた解放軍の少将が台湾の情報当局にこう進言した。
「後勤部の軍械部に席を置く劉連昆は、必ず落ちる。自分が彼をアモイに呼び出して協力を持ちかけてみる。奴は必ず落ちる」
台湾側の思想に共鳴してなびくと見たのではない。米ドルに転ぶと見立てたのだ。その頃、中台双方の軍で少将の称号を得ていたこの男の見通しの通りだった。軍械部長、劉連昆は、台湾に機密情報を提供すると約束した。こうして軍機と引き換えに巨額の資金を受けとるようになっていく。
李登輝発言をきっかけに、中国の防諜当局は、捜査の輪を次第に絞っていった。そしてついに劉連昆を台湾のスパイとして逮捕する。空のミサイル発射から三年が経った一九九九年のことだった。劉連昆は薬物注射によって処刑された。軍の高官としては最高ランクの死刑執行となった。
劉連昆をリクルートした少将は、死刑に衝撃を受け、あの「空砲」発言が情報源を危険にさらす結果を招いたと非難。中国に亡命して非を鳴らすといいたて身柄を当局に拘束されてしまう。
李登輝は、戦争の足音に慄く人々を安心させ、総統選挙をやる抜くために、「ミサイルは空砲だった」とあえて発言した。だが、インテリジェンスという手札をさらしてしまえば、必ず反作用が来る。国家が秘蔵する最高ランクの情報は内に獰猛な毒を孕んでいるのである。
株価安定作戦
ミサイルの発射によって台湾の民心を揺さぶる巧妙な手段とした。そして、できることなら、総統選挙で、李登輝を敗北に追い込みたい。中国政治局の内部文書は、北京の政治的な狙いを驚くほど率直に述べている。
「だからこそ、ミサイルの中身が空砲だったからといって、それを軽々に扱うわけにはいかなかった。あくまで、慎重には慎重を期する必要があったのだ。最近も、北朝鮮がミサイルを発射したが、何の目的でやったのか。その意図を正確に掴むことがまず優先されねばならない」
李登輝は、こう述べて、中国が放った四発のミサイルにどう応じて、台湾国内の動揺を食い止めたのか、その経緯を詳しく記した文書を示しながら、初めてその全貌を明らかにしたのだった。
ミサイルが撃ち込まれた場合に備えて、李登輝政権は「決策国議」という重要な機関を新たに行政院に置いた。対外的にどう対処するかを協議している。その具体的な背策は、このほど明らかにされた記録文書に網羅されている。
台湾の情報当局は、危機の二ヶ月前には、人民解放軍が総統選挙をにらんでどのように行動するかをまとめた中国側の極秘計画の概要を入手していた。このため、二月の段階で「臨時決策国議」を開いて、その対応策を早々と協議し、周到な準備に入っていたのである。これを受けた、人民解放軍の陸海空部隊が進出するとみられる演習区域の周辺に部隊が続々と動員され始めた。
李登輝は国民党の総統候補者として多忙を極めていた。このため、閣僚に協議を委ねて会議にはほとんど顔を見せなかった。代わって総統府からは、秘書長、国家安全会議の秘書長が出席した。行政院からは秘書長、新聞局長、国家安全局長が参加し、台湾省からは主席が姿を見せた。また各省からは、戦略正面を担当する内政、外交、国防の各閣僚、さらには、経済面の危機管理を担う経済、財政の各閣僚、大陸委員会の主任らが、前後八回にわたって会議を開いている。
株式市場への影響をいかにして最小限に食い止めるか―。一連の会議を通じて、最も重視されたのがこのことだった。全国を遊説に駆け回っている李登輝からも「株式市場の動揺を防ぐ。これに最大の意を用いてくれ」と指示が出されていた。
中国が弾道ミサイルを台湾周辺の海域に撃ちこめば、台湾の株式市場が動揺して、株価に影響が出るのは避けられない。「鄧小平が死んだ」という噂だけでも、株価が急落したほど、中国大陸の情勢に過敏に反応するマーケットである。そんな市場をどのようにしてなだめ、沈静化させるか、具体策が次々に検討されていった。
協議の結果、総額二千億台湾ドルにのぼる「株式市場安定基金」が創られることになった。そして、政権側は、株式相場が大きく荒れて暴落する様相を見せたときには、いつでも機動的に市場に介入して株を大量に買い上げる態勢を整えたのだった。そのための法令面の整備も進められた。
株は持っていないが、小口の預金を銀行に預けている庶民が、銀行の窓口に殺到したときにはどうするか。こうした銀行の取り付け騒ぎに備えて対策が講じられた。市中銀行に払い戻しの現金を豊富に用意させておく「リスクファンド」が設けられた。そのための資金として五百億台湾ドルが準備されたのだった。
ミサイルに驚いた一般の市民が家屋を投売りして、国外に脱出しようとしたときには、どんな沈静策を打ち出すのか。これには、不動産の価格が暴落しないよう買い支えの資金も用意された。このために、郵便貯金から三百五十億台湾ドルを拠出した。また、不安におびえる中小企業の経営者への臨時融資、さらには工業地区への安定化資金の提供までが検討された。そして、七ヶ月分の食糧も急遽備蓄される手際のよさだった。
これらの対策に必要な資金は、民営銀行、保険会社、郵便貯金、さらには労働者の退職年金基金までもが動員されて、台湾中からかき集められた。法令に従って投資期間内に巧みに運用されることになっていた。こうして株式市場を暴落から救う「安定基金」の大枠が着々と固められていった。
こうした有事への備えが功を奏して、ミサイルが台湾沖に飛来しても、マーケットに大きな動揺は起きなかった。いつミサイル演習が終るのか、分からない状況にあっても、株式市場の安定は保たれたのだった。
おそらく、有事に備えたクライシス・マネージメントとしては、イスラエルのような準戦時下にある国家を除いて、空前の規模のオペレーションだった。これほどの対策を必要とした危機が北京と台北の「京劇」でありうるはずはなかった。
「軍隊は軍隊で対策を講じなければならなかった。私は軍隊に、中国は本気で台湾を攻めてくる気はないはずだ。だが、その一方で、この機に乗じて台湾を攪乱させようとする恐れはある。それだけに、台湾側も、安全保障面にとどまらず、経済分野でも、密かに対応策を準備しなければならないと命じていました。われわれが、先方のミサイルに備えて部隊に大規模な軍事行動を命令すれば、いやがうえにも台湾の内部に不安が広がりますから」
ミサイル危機に臨んで、台湾の当局が、かくまで周到な準備態勢をしいて、ことにあたっていた事実は、アメリカや日本でも知られていなかった。
李登輝は、すべては、精緻なインテリジェンスが決め手だったと認めている。北京はミサイル演習を機に武力で台湾を侵す意図はもっていない。だとすれば、台湾を心理的に揺さぶって、選挙に影響を与えようとしているのだ。ならば、十全な備えでミサイル発射に備え、台湾の経済システムが動揺しないことを事実で示すことこそ勝利への道だと考えたのであった。
「先方が本当に武力で侵攻してくる構えを見せれば、別の対応策をとっていたことだろう」
李登輝は言葉少なに語っている。
エピローグ
隠棲の風情こそ、政客の品格を映しだす鏡―といわれる。確かにひとたび桂冠したひとは、権勢の街から身を遠ざけようとする。そして静謐のなかに逃れることで、まつりごとへの情熱を冷まそうとするのだろう。だが、権力への執着は断つことができても、国家に有益な存在でありつづけたいという内なる炎を消すのは容易ではあるまい。
李登輝もまたそんな政客のひとりなのだろう。総統の座を去って六年。東アジアの情勢について、いまなお飽くことなき関心を抱き続けている。そんな李登輝にとって、9・11事件のあと、超大国アメリカが突き進んだ道は危なげに見えている。そうしたアメリカの存在は、あの九六年危機をからくも乗り切った台湾海峡の波を再び高めようとしている。あの緊迫した日々の教訓はどれほど生かされているというのか―。その眼差しは決して穏やかなものではない。
「九六年当時、アメリカは台湾海峡の問題に非常に積極的だった。台湾の軍も、アメリカの機動部隊が果たしてくるのか。いつ、どこに来るか、はっきりとはわからなかったほどだ。だが、彼らは決然とやってきた。ところがいまね、アメリカが昔のようにこの地域に積極的な関心を持っているのかどうか、大きな疑問だ」
李登輝は、アメリカのイラク戦争での躓きがそれほど大きいと考えているのではないか。アメリカは、世界の二箇所半で起きる紛争に対応できるがゆえに、スーパーパワーと呼ばれてきた。だが、イラク情勢の混迷は、その力を殺いでしまった。ブッシュのアメリカは、中東の紛争に釘付けとなったまま、東アジアでの軍事上、外交上のプレゼンスをすり減らしつつある。
「台湾は軍事的重要性をもっている。その台湾がアジアにおける民主的な国家であり続けることは、アメリカにとっては非常に大事なわけだ。台湾が地上から消えてしまったら、アメリカの言う民主主義というのが国際社会で通らなくなってしまう。アメリカは、イラクに行くときも、民主化のためといっていた。別の問題があるにしてもね」
一方の台湾にとっても、超大国アメリカの関心をひきつけおくことこそが安全保障上、死活的に重要である。
「中国大陸は、台湾は中国の一部であり、中国の内政的問題だから、アメリカは何も口出しちゃいけないと言う。でもあれは口で言っているだけ。やっぱりアメリカの巨大な軍事力が恐いはずなんだ」
それゆえ台湾は、光り輝く真珠のような民主国家であり続けるべきだとこの老政客はいう。
「だがね、台湾における民主化の障害は、あのハンチントン教授によれば、私が十二年間で台湾を民主化し安定させすぎた。それがいま反動をよんでいるというんだ。それから指導者自身の問題も大いにあると思いますね」
東アジアの民主化は、それらの国々に自由と繁栄をもたらす。それが長く続くと、国家の長期的な安全保障より、目先の人気を優先させるポピュリズム政治家を生み出してしまう。その果てに超大国アメリカを自国だけの利益に回帰させてしまい、国家の将来を危機にさらしてはいないかというのだろう。
「いまの政府はアメリカと昔ほど密接じゃない。というか、よくないんだよ。九六年の危機のとき、われわれは公的にも私的にもアメリカと太い対話のパイプを持っていた。国家安全保障会議との関係は非常に密でね。いつでもコミュニケーションを取り合うことができた。民主党のクリントン政権とでさえ、カート・キャンベル国防次官補代理とプライベートな会合を続けていた。日本、アメリカ、台湾でよく情報を交換して回していた。アーミテージが中心になってね。あれは非常に役にたちました。それも私が辞めてから取り消しになった。いまの政府は、アメリカからの武器の購入問題にも手をつけていない。大きな問題です」
国家の行方を左右するインテリジェンスは、相手側から深い信頼をつなぎとめておかない限り、入ってこない。信念なきポピュリスト政治家が政権の座にあるときに、台湾海峡でかつてのような事態が起きれば、どうして危機を乗り切るのだろう。李登輝は慄然とせざるを得ないという。
「日米同盟に占める日本の役割が一段と高まってきている。アメリカに後ろを押されなくとも、日本自らが毅然として役割を果たせるようにならなきゃいけない。これが日本という国の責務じゃないかと思うんだ」
日本の新しい政治指導者には果たしてその責務を担う覚悟があるのだろうか、と李登輝は指摘する。北朝鮮による日本人の拉致問題こそ従来の日本政府の対応がいかに大きな問題を抱えているかを抉り出している、という。
「新潟の横田めぐみさんの拉致は深刻だ。僕は日本の若い人が拉致されたことに従来から重大な関心を持っていた。だから、私自身もいろいろと調べてみた。北朝鮮と交渉をした際、この人たちを何とかできないかと持ちかけてもみた。それにしても、日本政府の対応はもどかしかった。自分の国民が拉致されているにもかかわらず黙っている。これでは国家としての尊厳も何もなくなってしまう。拉致問題ひとつ処理できないのでは、弱すぎはしないか。武士道くらい発揮しろといいたい」
台湾と中国のあいだの内戦に終止符が打たれたのは一九九一年の五月のことだった。これを受けて台湾は、永く続けてきた臨時条款をようやく廃止した。それによって半世紀の永きにわたった独裁政治にようやく終止符を打ったのだった。李登輝は、こうして台湾を一歩一歩、民主的な国家に変貌させていった。
この国をそう導いていったことにいささかの悔いも迷いもない。だが、「李登輝の施政が台湾を民主化させすぎてしまった」というハンチントンの指摘は正鵠を射ているのかもしれない―。李登輝は、民主化の果てにやがて訪れるものが、危機に臨む覚悟の喪失であってはならないと考えている。このひとはいま「台湾に生まれた者の悲哀」をかみ締めているのかもしれない。
泰山木のように立ち尽くして見送ってくれたそのひとの内面からは、木の香りが立ちのぼっているようで芳しかった。