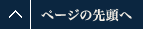慶応塾生新聞
「外交ジャーナリスト手嶋龍一氏に聞く『プロとしてのジャーナリズム』」
多くの塾生が憧れる業界の一つである「メディア産業」。例年数多の塾生がその狭き門をくぐって、ジャーナリズムの世界に足を踏み入れる。熱きジャーナリズム魂を秘めて、ペンとメモ帳を片手に街を駆け巡る事件記者の姿に自分を重ねる者もいるだろう。
だが、権力と戦い、世論を導いていく「プロフェッショナル」となるためには、それなりの覚悟が必要だ。それでもあえてジャーナリズムの世界に身を置きたいと思う塾生諸君に、稀代の塾員ジャーナリストからのメッセージをお届けしよう。
「ろくでもない学生新聞やマスコミ研究会でメディアの真似事をするほど閑なら、畳の上に寝転がって本でも読んでいたほうがずっといい」
インタビューの冒頭で飛び出した驚くべき発言。しかし、その言葉の奥には深い意味が込められていた。
今回われわれは、NHKのワシントン支局長を永くつとめ、現在は外交ジャーナリスト・作家として多方面で活躍している手嶋龍一氏(昭和49年経済学部卒)に、「プロフェッショナルとしてのジャーナリスト」をテーマに話を伺った。手嶋氏はワシントンで同時多発テロ事件に遭遇し、事件発生時から11日間連続で現地からのリポートを行ったことで知られている。
手嶋氏は、いまの日本では真にプロのジャーナリストと呼べる人材は滅び行く稀少種だという。新聞もテレビ・メディアも巨大な組織から離脱しても個として生き抜いていけるようなジャーナリストはイリオモテヤマネコのように少ないという。
ジャーナリズムの世界で一人の記者が「プロフェッショナル」として生きる。そのためにはどうしても身につけておかなければならない「最低限のスキル」。手嶋氏は、その絶対値を「時速百五十キロ級の剛速球」と定義する。
「時速九十キロの球しか投げられない選手が大リーグのマウンドに立つことはかないません。ジャーナリストにとっての剛速球とは、原稿を素早く、正確に、そしてすっきりとした論理と文体で書きあげる能力をいう。だが、こんな潜在力が内に眠っているかどうか、誰にもわからない。断っておきますが、僕にもそんな力の片鱗があるのかどうか、いまだにわかりません。ただ、そうありたいと願っているに過ぎません」。
だが同時に、手嶋氏は、ジャーナリストとしての基礎体力が備わっているだけでは、歴史の証人として、現代史の瞬間に立ち会う資格がないという。
「ジャーナリストの本質は歴史が紡ぎだされていく現場に居合わせて、歴史の赴く方角を人々に簡潔に報告することにある。だとすれば、基礎体力だけでは心もとない」。
中国革命の胎動を伝ええたエドガー・スノー、世界を変えたモスクワの11日間を報告したジョン・リード、ベトナム戦争の過てる指導者たちを描いたデビッド・ハルバースタムの著作を思い浮かべて話してくれた。
だからこそ、手嶋氏はジャーナリズムの世界を志す若者たちに「瑣末なマスコミの知識より旅や読書を通じて新しい世界に触れ合うほうがいい」と語る。
「『歴史の証人』というけれど、これが難しい。現場に居合わせるだけでは、交通事故の目撃者と変わらない。逆説的な物言いになりますが、現場に居合わせたがゆえに、対象に近すぎて事態が見えないこともある。自分の目撃をもいちど冷たく突き放し、大きな文脈の中でその意味を考え直してみる。これが我々の仕事なのです。だから、歴史に対する洞察力をうちに育んでおかなければ。当歳のディープ・インパクトを知っていたのですが、走るかどうかは、わからなかった。ただ、素質の片鱗は窺えました。初々しい歴史観がどこかしらに秘められている―そんな若駒は、メディアに向いているかも知れません。でも人生はギャンブルです。やってみなければわからない。だから寝転んで。『ローマ帝国衰亡史』か『史記』でも読んで閑つぶしをしてはどうでしょう」
憧れだけでは決して到達することのできない世界。それがジャーナリズムの世界を志す者へのメッセージ。それは、厳しさと同時に温かさをも内包するものであった。