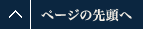「アラン島の人々」
僕は島で暮らすひとたちが好きだ。とりわけ小さな島に住むひとたちからは、そこはかとない温もりが伝わってくる。ジャーナリストとして、アメリカ大陸の山岳地帯を、ヨーロッパの都市を、アジアの辺境を旅した体験から、やはり島はいいなと思う。
いまの僕に時間のやりくりがつくなら、迷わずアイルランド島のダブリン行きの航空券を買うだろう。それほどに緑なすあの島はきらきらと輝いて魅力的だ。だが、ヨーロッパ大陸の西端に位置するアイルランド島は、気候に恵まれているわけでも、豊かな食材があるわけでもない。真冬は鉛色の空が頭上にのしかかり、午後三時を過ぎるともう陽が落ちてしまう。真夏の夜は午後八時を過ぎても明るいのだが、日中はたちまち雨雲に覆われ時雨模様となる。にもかかわらず、ひとたびこの島を訪れると、その不思議な魅力にとり憑かれてしまう。そこかしこに妖精が潜んでいると土地の子供たちは信じており、大人たちの面差しもどこか夢見るようだ。
大西洋に剣のように突き出たディングル半島を訪ねたときのことだ。誤ってわき道に迷い込んでしまった。田舎道を行くお年寄りを見つけて尋ねてみた。だがどうにも英語が通じない。この一帯の人々はゲール語で日々の暮らしを営んでいるからなのだろうか。ルート・マップを広げて指差しているうち、この人の耳がまったく聴こえないことに気づいた。だが、この老人はそんなことなど一向に気にする風もなく、しわが深く刻まれたその顔は「俺の後について来い」と無言で語り、農具を左手に持って悠然と歩き出した。彼の後姿は優しさに満ち溢れ、古代ケルト兵士の気高さを漂わせていた。
おかげでようやくディングル半島にたどりつくことができた。目指すアラン諸島が海霧の彼方に荒々しい姿を垣間見せていた。ゴールウェーの港から小さな汽船に乗ってイニュシュモアと呼ばれるアラン本島に向かう。距離にして三十マイル、三時間近い行程だった。沖合に出るとたちまち深い霧に覆われ、汽船は大波に木の葉のように翻弄されてしまう。それほどに北の海は猛々しい。藍色のアラン・セーターを着た三人の漁師が乗り合わせていた。海で遭難しても身元が判るようにとそれぞれに異なった織り柄を身につけているという。汽船がキラーニー湾に入るとようやく揺れが収まった。そこは透き通った静寂の世界だった。
テレビ・ドキュメンタリーの制作に携わる者なら誰でも生涯にいちどこの地を訪ねてみたいと願うだろう。アイリッシュの血をひくアメリカ人監督、ロバート・フラハティによって撮影された『アラン』。この一作によって映像ドキュメンタリーはその幕を開けたからだ。烈風が吹きすさぶなか、大西洋を見下ろす断崖で農夫はつるはしを振りおろし岩盤をたたき割る。ジャガイモを栽培する土を創り出しているのである。これほど過酷な自然がどこにあろう。こうして手にした命の大地も海から吹きつける風でたちまち飛び散ってしまう。そして男たちは、再びつるはしを振りおろす。『アラン』はこんな島の暮らしをフィルムに刻んで、不朽の名作を世に送り出したのだった。
この旅でアラン島から持ち帰った岩盤のかけらをいまも机の片隅にしまっている。そして心衰えたとき、アラン島の石片を手にとってみる。するとあの小さな島の光景が蘇ってくる。たちまち烈風が吹き荒れ、白波をけたてて沖の漁に向かうアラン・セーターの男たちの意志的な面構えが立ち現れる。この島の人々は、海で暮らしをたて、陸に帰っては、父親が、祖父がたたき割った土を烈風にさらわれまいと、石垣を営々と築きあげた。そしていまでは立派なジャガイモ畑を作りあげた。人間とは何と偉大な生き物なのだろう。僕もあのアラン島の人々のように、生きたいと思う。
2007年4月3日掲載