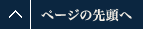利害を超えた縁の深まり
「ダーナ」春号特集「縁は味なもの」
ネットワークを張り巡らせ、集めたインテリジェンス(情報)を駆使し、未来を冷徹な目で予測する手嶋龍一さん。NHKの特派員を経て、外交ジャーナリスト・作家として世界の事象を見つめ続けてきた手嶋さんが感じる縁の世界とは――。
始まりは一本の電話から
――外交ジャーナリストとして活躍される手嶋さんですが、「縁」を実感されることも多いのではないですか?
人間という生き物は、ほんとうに人と人とのご縁のなかで生かされていると感じます。僕が身を置いてきニュースの世界も同じです。
僕は、海外のニュースを専ら扱う外信畑の記者ではなく、政治部の記者でした。
ですから、海外に赴任することなど考えたこともありせんでした。ですから、三十代の半ばに、突然、「ワシントンに特派員として赴任しろ」と言われても、「ちょっと待ってください」と戸惑ってしまいました。こちらは、何の心構えも、赴任の準備もしていないわけですから。
でも、そこが僕のまことにいい加減なところなのですが、「まあ、いいか」とすぐに観念しました。もともと、組織人としては、適性を欠いていましたので、どの部署でどうしたいなどという希望は抱いたことがなかったのです。どうもいい加減で済みません(笑)。
そんなわけで、彼の地にワシントンに辿りついてみたのですが、ワシントンは世界で最も錯綜した情報都市ですから、それは仰ぎ見るような難攻不落の城でした。何の準えもなくそこに挑むのは、無酸素でエベレストに登頂するような無謀なわざでした。
僕はどちらかといえば、ダメなときはジタバタしない性質なのです。まあ、布団を被って寝ているほうです。視聴者にもろくなニュースをお届けできない。ご迷惑をかけていますから、「早々に店じまいにしなければ」と思っていたわけです。
そんなある日、私のデスクの電話が突然鳴ったのです。「ジェファーソン・ホテルに出てこい」と言うのです。見知らぬ相手でした。が、話す言葉が、アメリカン・イングリッシュじゃない。イギリスの、しかも、高等教育を受けた知的な英語でした。
――まったく知らない人に呼ばれて、その場所に行かれたんですか?
はい、ワシントンでは、手も足も出ないのですから、暇を持て余していましたから(笑)。
そのイギリス人は「この街はなかなか厄介だろう」と同情してくれました。「素人が、それも素手でやってくるようなところじゃありません」と応じ、そろそろここを失礼しようと思っていると正直に打ち明けました。ところがこの人物は「まあ、そう慌てたものでもないだろう。この人に会ってみなさい」とメモをくれたのです。情報の魔都ともいうべきワシントンへの地下水脈に入っていくキー・パーソンを紹介してくれたのでした。「大丈夫、ちゃんと段取りはつけてある」と淡々としていました。
見知らぬ僕に、何故、これほどまでに、親切にしてくれるんだろう―そのとき「もしかしたら」と思いあたる節がありました。あのひとが借りを返そうと思ってくれたのかもしれないと。
政治部記者として、永田町で仕事をしていた頃のことです。親友の英国人が、駐日英国大使の補佐官をしていたのです。大使は東アジアの安全保障の専門家でしたが、通商問題には必ずしも明るくありませんでした。当時、日英間には、英国産のウイスキーの関税引き下げをめぐって、厳しい交渉が行われていました。大使は苦しい立場にありました。
そのご苦労を親友から聞かされ、「それなら、親しくしている政府の税制調査会の委員、当時、暴れ馬と呼ばれていた委員に頼んでみよう」と約束したのです。
込み入った問題ですから、簡単に解決するはずもありませんが、その暴れ馬も「じゃあ、少し動いてみよう」と言ってくれました。答申の文書を、それも形容詞を、ほんの少しだけ英国に有利に見えるよう書き換えてくれたのでした。
親友との友情に鑑みて、少しだけお手伝いしたにすぎなかったのですが、大使は「いつか必ず、あなたには恩返しをさせていただく」と言ってくださった。しかし、そんなことはすぐに忘れてしまいました(笑)。
この英国大使は、僕がワシントンに赴任そたと親友から聞いて、さぞかし困っているにちがいないと同情してくださったのでしょう。私にとって、大きな転機になる情報の金鉱脈に誘ってくれたのです。御縁とはなんとありがたいものなのでしょう。
外交ジャーナリストとして今の僕があるのは、この縁のお陰といっていいかもしれません。人脈というのは、これはというひとりの人物にいきあたると、あとはあっと言う間に広がっていくものなのです。あとは芋づる式に収穫すればいい(笑)。ホワイトハウスからペンタゴン、国務省にと一気に重要人物とのネットワークが広がっていきました。
大切な「一期一会」の精神
――縁が広がっても、そこから重要な情報を入手するのは、難しいことではないですか?
僕のような仕事では、「知っている」は「知らない」と同義語なのです。
平たく言うと「知っている」というのは、例えば同級生であったり、面識があったり、名刺を交換したり、という間柄にすぎません。文字通り「知っている」にすぎない。これでは、いざという時には、力になりません。
相手とは、ときに命にも関わるような、重要な情報をやりとりするのですから、なまなかな関係では、胸の内をあかそうとしません。よほどしっかりした絆で結ばれていなければ、真に大切なインテリジェンスをやりとりすることはできません。
深い友情、強い絆が求められます。試練を経た友情こそが、真の友情たりえるのです。
人脈をひたすら広げることだけを考えていても、時間も体力も足りなくなります(笑)。
広げるのでなく、大切なご縁を一生かけて深めていくような気持ちが大切です。
「良い縁だ」とか「悪い縁だ」とか、短期的に見た利害関係では、縁を深めることはできません。いっとき悪い縁だと思っても、深めることで良い縁になることもあるはずです。
――「縁」には人との出会いも含めた意味合いがあります。今の日本は、人間関係が希薄になっていると感じませんか?
そうですか? だとしたらとても悲しいことです。
もともと日本は、「一期一会」を大切にする良き伝統があります。
肩書きだとか、学歴だとかを超えた、お付き合いのできる素地がそこかしこにある。人として、素晴らしい価値観を育む環境があります。それは、温もりのあるコミュニティーによって育まれる。
世界中の国々を見てきて感じることですが、アメリカであれ、アフリカであれ、名もなき人々のなかに立派な人格を持った人がたくさんいる。それは、温もりのあるコミュニティーが生み、育てるのでしょう。そんな地域社会者を持っている国は、基礎の土台がしっかりしていて、やがて大きく羽ばたいていきます。それが国の力というものです。
そういう国にこそ、揺るぎないアイデンティティーをもった、そう、リンカーンや坂本竜馬のような、成熟して、スケールの大きな人間が育まれると思います。
杉原千畝が残した「縁」
――コミュニティーがしっかりしているということは、人々が「縁」を大切にしているという表われなんですね。
そうだと思います。日本だって、そういう環境がしっかりあったと思います。
たとえば江戸時代の下町や長屋の暮らしに代表される「人情」のあるコミュニティーです。道をはさんで向かいの家にも声が届くくらいの距離で人々が生活し、濃密な人間関係を築いていた。困ったときはお互いに助け合って暮らしていた。そういう素地のなかから、偉大な人間が生まれるのだと思います。しっかりしたコミュニティが、高杉晋作や西郷隆盛のような、国をも変える志士たちを生みだしていきました。
世界の歴史の長さを考えると、明治維新はつい最近のことなのですが、あのまことに小さな国が一気に近代国家へ脱皮するのを主導した人材が、あの時期に数多く出現しました。その遺伝子は私たち現代の日本人に受け継がれているはずです。そんな日本に生まれたことに誇りを持ちたいと思います。
語学に長けているとか、いないとかではない。やはり、日本という国の背景をしっかりと備えた人格をもっている人を国際人と呼ぶべきなのです。そんな人材こそ世界に通用する。
――作家としても活躍されていますが、最新作「スギハラ・ダラー」のスギハラは、「日本のシンドラー」と呼ばれる杉原千畝(ちうね)さんだそうですが、世界に認められる一人ですね
第二次世界大戦下の一九四〇年、杉原さんは、リトアニアの首都カウナスで、日本領事館領事代理を務め、ナチスドイツによって国を追われたユダヤ人約六千人を救った人です。
彼は、日本政府の訓令を無視する形で、日本領事館が閉鎖されるぎりぎりまで、ユダヤの人々を救うため亡命ビザを発給し続けました。
この一人の日本人の決意、志によって助けられた人が、戦後の、自由な経済、自由な市場を創り作り上げていったのです。国境をも超えた自由な経済のシンボルは「ユーロ・ダラー」に象徴されますが、それがスギハラという勇気ある日本人によって生みだされた。そんな想いを籠めて、新作のタイトルを『スギハラ・ダラー』と命名しました。
杉原さんに助けられた人物は、作中、名前は変えてありますが、実在する人をモデルにしています。
その方にお会いしたとき、「私は、杉原千畝に命を助けられた『スギハラサバイバル』の一人です。だからこそ、私は自由を大切にしたい」という言葉を聞いたとき、日本人として非常に感銘を受けました。
たった一人の日本人の立派な志が、よき縁となり、いまなお世界に影響しているわけです。これは、とてつもなく壮大な話だと感じ、いつかは筆を執ろうと思っていました。
まずは、自分の暮らす町で、人との出会いや、ふれあいを大切にしたい。そんな気持ちが、一つの種となって沙漠を緑なす大地に変えていく。それがさらなるご縁となって、世界中に広がっていくはずです。