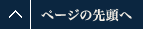米中対立時代 日本に求められる戦略
力を増す独裁制と機能不全の民主主義
二〇一九年の国際政局は、「トランプのアメリカ」と「習近平の中国」という二つの大国が太平洋を挟んで対峙する「米中衝突」の構図のなかで推移していくことになるだろう。
アメリカや中国のように、広大な国土と多様な人々を率いていく大国のリーダーは本来、くっきりとした理念と、それを実現していく軍事力をはじめとする「力」を内に備えていなければならない。理念と権力を併せ持った政治家でなければ大国を統治していくことはかなわない。アメリカならウィルソン大統領、中国なら毛沢東がまさしくそうした政治指導者だった。
だが、いまの米中両国のリーダーは、強力な権力こそ手にしているが、それぞれの風土に根差した理念をその精神に湛えているとは言い難い。それゆえ、現下の情勢を少数の指導者が強大な権力を振るう「独裁の宴」だと言い表してきた。
アメリカのドナルド・トランプ氏こそ、独裁の時代を代表する「異形の大統領」なのである。アメリカ大統領は飛びぬけて強力な陸・海・空・海兵の四軍を率いる最高司令官であるばかりではない。時に大統領令を発して議会をもねじ伏せる力を有している。これは歴代の大統領にも与えられてきた権力だったが、トランプ大統領は、それらの権力をどのような理念に拠って行使しているのかが不明なのである。問題の本質はこの一点にあると言っていい。アメリカの国益を何より優先する「米国第一主義」は、理念なのではなく、個々の政治決断の結果に過ぎない。
中国の習近平国家主席の場合も外側を覆っているイデオロギーに惑わされてはならない。その素顔は驚くほどのリアリストなのである。政治家を目指すにあたって、中国共産党の掲げる理念に心惹かれたからでなないと明け透けに側近に語っている。中国は一党独裁であり、政治権力を目指そうとすれば「他に策はなかった」というのである。
二〇一七年十月に開かれた、五年に一度の共産党大会で、共産党の憲法ともいえる「党規約」に、毛沢東、鄧小平と並んで習近平「思想」が盛り込まれた。毛沢東はそのあまりに過剰な思想性から文化大革命という未曽有の混乱を中国にもたらしたが、それを毛沢東思想と呼ぶことに反対する人はいないだろう。だが図抜けた現実主義者の習近平氏に「思想」を冠するのは皮肉にさえ映る。理念なき独裁色が際立っている。
本来、国家の戦略は、指導者が掲げる理念に導かれて生み出される。だが、異形の大統領、ドナルド・トランプ氏の場合は、理念などみじんもいなく、それゆえ戦略も定かでない。これほど無定形のアメリカ指導者はかつていなかったろう。外務省の元主任分析官、佐藤優氏が、私と編んだ対論本のなかで「彼(トランプ)は何に衝き動かされているのかというと、ユング心理学の言葉を借りれば『集合的無意識』ではないかと思うのです。簡単に言うと、『個人の意識の領域を超えた民族などの集合の持つ無意識』です」(『米中衝突』中公新書ラクレ)と喝破している。「集合的無意識」は究極のポピュリズム(大衆迎合主義)の推進エンジンなのである。
二〇一九年はこれまでにない危うさを秘めた年になる。そんな予感を持たざるを得ないのは、独裁の対極にあって、世界を安定させてきたはずの議会制民主主義がいま機能不全に陥っているからだ。冷戦期には、スターリニズムという独裁制に対し、アメリカやイギリス、日本などの西側諸国は議会制民主主義を堅持して拮抗していた。
ところが今、イギリスのメイ首相はブレグジット(イギリスの欧州連合離脱)の混迷の中にあり、ドイツのメルケル首相も移民・難民問題によって窮地に立たされている。西欧諸国では、反移民の極右勢力が急速に頭をもたげつつある。複雑化する現代世界にあっては、民主主義が、とりわけ代議制が十分に機能していない。むしろ決断が迅速で、草の根の感情に寄り添った、独裁的な政治手法が力を得ているようにみえる。
だが、議会制民主主義にも一種の独裁的な権力行使という要素が内包されている。それは必ずしも負の要素ではない。選挙で有権者から民意を託された宰相は、国家運営の強力な権限をもつ。国民が自分を選んだからには、わが決定に従えと命じる。そしてその政治判断が誤っていれば、有権者は次の選挙で権力の座から追い落とせばいい。
それゆえ、有権者が直接民意を明らかにする「直接民主制」には、時に毒が含まれている。第一次世界大戦のあとに誕生した世界で最も民主的といわれたドイツのワイマール憲法。そこには直接民主制の要素が多く埋め込まれていた。それが後にナチズムの台頭を生んだことは広く知られている。イギリスは一六年六月、欧州連合を脱退するかどうかの選択を国民投票に委ねてしまった。その結果、ブレクジットが決まり、それが今に至る混迷を生んでいる。
議会制民主主義のシステムを経て選ばれた政治指導者が、孤独のうちに決断する。かかる独裁的な要素は、政治のリーダーには欠かせない。だからこそ、一国のリーダーには崇高な理念と百万人といえども我ゆかんという決断力が求められる。一方で理念よりも力に依拠する独裁的なリーダーが増え、他方では議会制民主主義が機能不全に陥っている。いまの世界の危機は、独裁と民主性の二つながらにあると心得るべきだろう。
冷戦時代より危機は身近にある
世界史的な視点で見ると、十九世紀半ばから二十世紀初頭にかけて隆盛を誇ったイギリスに、ドイツが挑戦することで二度の大戦が起こった。
いまメディアでは「中国の台頭」という言葉がよく使われるが、世界史的に見れば「台頭」ではなく「復活」である。中国が世界の中心の座から退いたのは、一八四〇年に起きた阿片戦争でイギリスに敗れて以降のことである。阿片戦争以前の一八二〇年時点では、中国(清)は世界のGDP(国内総生産)の三分の一を占めていたとの推計もある。しばらく主役の座を降りていた中国が復活し、アメリカが支配する世界に挑んでいる。これが世界史的には正しい認識になるし、少なくとも中国の人々はそう確信している。
中国に対して、二〇一八年十月四日、アメリカ副大統領のマイク・ペンスはハドソン研究所で演説を行い、「米中対立」の時代に入ったことを宣言した。ペンス演説では、中国の習近平政権を、アメリカからハイテク技術を掠め取る「メイド・イン・チャイナ2025」を推し進め、「一帯一路構想」によって近隣諸国を債務で搦めとっているなどとして厳しく言及。さらに、ウイグル人やチベット人などの少数民族の抑圧や、南シナ海への軍事進出なども非難した。個々の事象ではなく、中国という独裁国家そのものを認めない、というトーンに貫かれていた。
いまや米中の対立は貿易摩擦にとどまらない。東アジアの海を舞台にした軍事対決の様相を帯びはじめている。南シナ海は、中国は「内海」だと主張している。だが、アメリカは、公海での航行の自由を身をもって示すため、南シナ海にイージス艦「ディケイター」を派遣した。中国海軍の駆逐艦はこれを迎えて、わずか四一㍍のところまで異常接近した。一八年九月三十日のことだ。通常、敵対する艦船は二㌔以内には踏み込まない。米中の両海軍は一触即発の水域に近づこうとしている。
こうした緊迫した情勢を反映して、アメリカのメディアには「新冷戦」「冷戦Ⅱ」という言葉が溢れている。だが、その表現は果たして適切なのだろうか。そもそも「冷戦」とは、米ソが対峙し、周辺部では朝鮮半島やベトナム戦争といった「熱戦」に発展したが、冷戦の戦略正面たるヨーロッパでは熱戦に至らなかった。とりわけ、核兵器による熱戦をかろうじて免れた。それゆえに「冷たい戦争=冷戦」と呼ばれたのだった。
だが欧米のメディアは「新冷戦」と呼ぶが、かつてのように核戦争が起きない保証はあるのだろうか。否と言わざるを得ない。冷戦期に存在した核戦争を防ぐための二つの装置、ABM(弾道弾迎撃ミサイル)制限条約とINF(中距離核戦力)全廃条約のいずれがいまや事実上存在しないからだ。
ABM制限条約とは、大陸間弾道ミサイルへの防衛手段を敢えて制限しようとするものだ。大陸間弾道ミサイルでは精緻な軍事目標を狙えないため、標的は敵の大都市にならざるをえない。米ソの最高指導者がひとたび核ミサイルの発射を命じれば、迎撃システムが制限されているため、夥しい数の国民が犠牲になるのは避けられない。お互い国民を核戦争の「人質」として差し出すことで、指導者が核のボタンを押すことをためらう「恐怖の均衡」を敢えてつくりだしたのだった。二〇〇二年六月、ジョージ・W・ブッシュ政権は、ABM制限条約から脱退している。
もう一つのINF全廃条約は、一九八七年十二月八日にアメリカのレーガン大統領とソ連のゴルバチョフ書記長によってワシントンで調印された。当時、私は特派員として調印の瞬間に立ち会った。だがそれは触れれば崩れ落ちてしまう脆い土台の上の合意だった。
冷戦さなかの一九八〇年代、ソ連は西ヨーロッパ諸国を標的にSS―20という中距離ミサイルの配備に踏み切った。当時のアメリカの指導者は深刻なジレンマに立たされることになった。ソ連の中距離ミサイルはアメリカには届かない。にもかかわらず、西側同盟職を守るため対抗措置をとるのか。これは今、北朝鮮の中距離核ミサイルが日本を射程に収めている状況とぴたりと重なる。アメリカは西側同盟の盟主としていかに行動し、責務を果たすかを問われている。結局、当時のアメリカ含むNATO(北大西洋条約機構)は、ソ連に対抗してパーシングⅡミサイルの配備を進めつつ、同時にINFの削減を目指した交渉をソ連側と始めることを決めた。いわゆる「NATOの二重決定」がそれだった。その果てにINF全廃条約が締結されたのだった。
トランプ大統領は、そのINF全廃条約からも、二〇一八年十一月の米中間選挙の際、核兵器開発の揺籃の地ネバダ州で離脱を表明してしまった。あの冷戦の時代、核戦争を防いだ二つの条約から、アメリカは離脱したのである。
冷戦期の米ソ対立の主な舞台はヨーロッパだった。だが現在では、米中対立の最前線は東アジア・太平洋に移っている。北朝鮮、ロシア、中国の中距離核ミサイルの主たる標的は、日本列島であり、在日米軍基地に他ならない。日本にとっては、二重の意味で、あの冷戦の時代より危機は身近にある。「新冷戦」などと安易に呼ぶわけにはいかないことを日本の人々は自覚すべきだろう。
朝鮮半島の南北融和 対馬海峡が最前線に
朝鮮半島情勢も錯綜し、混迷の度を増している。二〇一八年六月十二日、シンガポールで米朝首脳会談が行われた。この会談によって米朝和解が実現し、朝鮮半島の非核化が進むと多くのメディアは好意的に評価した。北朝鮮は「朝鮮半島の完全な非核化に向け取り組む」と約束したのだが、会談から半年以上が過ぎても、核の廃棄は一向に進まない。非核化の期限、工程、査察のいずれも実現していない。
一方で、米朝首脳会談の実施は、北の強権体制をトランプ政権が裏書し、先制攻撃の危険を取り除いた。現に米韓合同軍事演習も行われていない。さらに、非核化の費用を韓国と日本が支払うことに道をつけた。北朝鮮は自ら何らカードを切ることなく、三つの重要なカードをトランプ政権から引き出してみせた。これらの動きを冷徹に判断すれば、北は本格的な核廃棄に応じる意思がないと言わざるを得ないだろう。二度目の米朝首脳会談が実現しても、大きな進展は望めまい。
これまで、朝鮮半島は三つのラインによって分断されてきた。中朝の国境、南北の境界(三八度線)、そして朝鮮半島と日本を分かつ対馬海峡である。中朝のパイプ役であり北朝鮮のナンバー2でもあった張成沢氏の粛清によって、中朝関係は緊張し、一時は高い障壁となっていた。だが習近平政権が米朝首脳会談に臨む金正恩委員長の後ろ盾となったことで、中国と北朝鮮はいま極めて親密だ。
次に北朝鮮と韓国の関係も、一八年四月の南北首脳会談を皮切りに一気に接近している。板門店宣言のなかには「鉄道、道路の南北連結事業の推進」が謳われるなど、経済制裁を無実化させる事柄も進んでいる。日本に対する徴用工訴訟の問題も含めて、三八度線という南北のラインも障壁ではなくなりつつある。その結果、境界線は対馬海峡にまで南下しつつある。対馬から韓国・釜山までは高速フェリーでわずか一時間あまりの距離だ。日本は背後に中国が控える朝鮮半島と角突き合わせる最前線に置かれてしまったのだ。
こうした中で、日本外交にとって重要なファクターに「プーチンのロシア」がなりつつある。一八年九月に行われたロシアの大規模な軍事演習「ヴォストーク2018」に中国軍が参加した。中露が軍事的な連携に入ろうとしていると日米に示す狙いがあったのだろう。
日本はいま、ロシアとどう対していけばいいのか。安倍晋三首相とロシアのプーチン大統領は一八年十一月にシンガポールで会談し、一九五六年の日ソ共同宣言を基礎に今後平和条約の締結交渉を加速することで合意した。北方領土に関しては、歯舞・色丹の二島を先行して日本に引き渡す選択肢が視野に入ってきた。
元外務次官の竹内行夫氏は、「今回の合意は、日本の外交努力や成果を後戻りさせるものだ。日本政府は、国後、択捉を含む4島の帰属問題をロシアに認めさせるよう努力してきた経緯がある。4島の名前を列記し、その帰属の問題を解決して平和条約を締結するとした93年の東京宣言は無視された」(「朝日新聞」十一月十六日付朝刊)と批判している。
この批判は、対ロ情勢の変化という視点を決定的に欠いている。ソ連の崩壊直後の情勢と現在では、対ロ交渉の戦略も変えざるを得ない。竹内氏は「東京宣言」を成果として挙げているが、日本外交はそこを突破口にできなかったのである。日露の喉元に突き刺さった棘を抜いておけば、接近を図る中露にくさびを打ち込むこともできる。刻々と変化する国際情勢からことさら目を背けて、従来の国会答弁との整合性などをあげつらっても、北東アジアに新たな足場は築けない。
目的と戦略を見誤るな
私は北海道出身であり、北方四島は歴史的にも国際法上も、日本の密接不可分の領土であるという主張を曲げたげたことはない。だが外交ジャーナリストとして、現実的な外交の選択肢を示す責務を負っている。いまこそ、歯舞。色丹の引き渡しを実現し日露の領土問題に区切りをつけ、国後・択捉は継続して協議する枠組みを作るべき時だろう。
日本という国がいま国際社会でいかなる立場に置かれているのか。それを等身大で伝える責務を日本のリーダーは負っている。明治期のリーダーたちは、ポーツマス条約で日露戦争の賠償金が得られず、日比谷で焼き討ち事件が起きても、「これがわが日本の力の限界だ」と論じてひるまなかった。厳しい現実を説明し続けた。そういうリーダーがついこの間まで日本にも存在したのだ。
最後に、見習うべきリーダー像として、第一六代米大統領エイブラハム・リンカーンを挙げたい。米イェール大学のギャディス教授は、南北戦争という国家の激動の最中も、「合衆国の統一」という最上位の目的を見失わなかったと指摘する。
「リンカーンは、自らが覚悟を持って引き受けたこの内戦が、奴隷制度によって穢されたアメリカという国家の魂を救う手段になるとも見抜いていた。 とはいえ、まず救わねばならないのは国家のほうである。魂の救済を最優先にするのは預言者であって政治家ではない」
奴隷解放を性急に進めれば、国家が分裂してしまう。合衆国の統一こそ重要であり、その目的を達するための戦略とバランスをリンカーンは読み誤らなかった。 米中対立により激変する東アジアにおいて、日本はいかなる目的と戦略をもって進んでいくべきかを決断する時だ。われわれ日本に残された時間は限られている。
【プロフィール】ロシアのプーチン大統領も、強大な権力をもっている。しかし、かつての旧ソ連には、その是非はともかくとして共産主義という理念が存在した。現在のロシアには、冷戦後の新しいロシアをどのように率いていくかという理念は見えてこない。
他にも、サウジアラビアのムハンマド皇太子、トルコのエルドアン大統領など、独裁色の強いリーダーが国際社会で存在感を増している。後述するが、北朝鮮の最高指導者である金正恩もその典型であろう。
手嶋龍一
てしま・りゅういち(外交ジャーナリスト、作家)
一九四九年北海道生まれ。慶應義塾大学卒業後、NHK入局。9・11米国同時多発テロにNHKワシントン支局長として遭遇する。ハーバード大学国際問題研究所フェローを経て二〇〇五年に独立。ベストセラーになったインテリジェンス小説『ウルトラ・ダラー』や、作家・佐藤優氏との共著『米中衝突 危機の日米同盟と朝鮮半島』など著書多数。