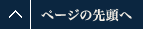「大統領の料理人~厨房からのぞいたホワイトハウス11年」
ウォルター・シャイブ 著
解説 ホワイトハウス饗宴の演出者
ホワイトハウスの中庭から大統領専用のヘリコプター「マリーン・ワン」に乗り込こむリチャード・ミルハウス・ニクソン。天を睨んで傲然と手を振る最高権力者の表情をいまも鮮やかに憶いだす。大統領の側近たちがウォーターゲート・ビルの民主党全国委員会に盗聴装置を仕掛けたことが発端となって、共和党政権は次第に追い詰められていった。政治スキャンダルによって大統領職を泥に塗れさせた責任を問う声が巷に溢れ、強気のリチャード・ニクソンも遂に白い館を明け渡さざるを得なくなってしまう。
わがニクソンの時代が歴史に評価される日は必ずくるはずだ―。
ホワイトハウスを去る大統領の暗い瞳はそう語りかけていた。
大統領辞任の決意を固めた運命の日。リチャード・ニクソンは寝室をそっと抜け出し、キッチンにひとり降りていった。そして、大型の冷蔵庫を開けて牛乳のボトルを取り出し、コップに注いでぐいと呑み干した。身辺の警護に当たるシークレット・サービスが真っ先に追いかけてきた。ついで朝食を用意するはずだったシェフが駆けつけてきた。彼らはそこで、巨大な権力を手放そうとしているひとりの男のぞっとするような形相を見てしまったのである。
テレビカメラの砲列が居並ぶヘリポート。
いまだ夜が明けやらぬホワイトハウスのキッチン。
公の歴史として刻まれていく常の舞台は前者である。だが権力者が一瞬ほんとうの貌を曝け出す私的な空間は後者なのだ。大統領職を離れたリチャード・ニクソンは、後に見事な筆遣いで辞意を固めた瞬間を書き残した。そのため、われわれは牛乳瓶のエピソードを知っているが、シークレット・サービスやシェフは、常の場合なら職業上の嗜みのゆえに黙して語らない。
本書の著者ウォルター・シャイブは、ホワイトハウスの厨房で起きた出来事を詳しく語った初めての『大統領の料理人』なのである。それは白い館で演出される饗宴外交の最前線を描ききったルポルタージュだ。この腕利きの料理人は、ビル・クリントン四十二代大統領とそのファースト・レディ、ヒラリー・クリントンに仕えた。さらにはジョージ・W・ブッシュ四十三代大統領とそのファースト・レディ、ローラ・ブッシュにも仕え、二つのまったく異なる時代を生き抜いたのだった。
『大統領の料理人』は、モニカ・ルインスキー事件が明るみに出た朝、クリントン夫妻がどんな表情で食卓を囲んでいたかを描いているわけではいない。本書の冒頭で政治向きのことには触れないと断っている。だが、それゆえにこの本はリアリティに満ちている。
「インテリジェンスの教科書」は、しばしば料理を例に引いて、情報の世界を解説する。料理の素材と見事に仕上がった皿。両者の間柄は、雑多な一般情報を意味する「インフォーメーション」と精緻な分析が加えられた「インテリジェンス」の関係にたとえられる。いかに旬な素材でもそれだけでは客をもてなす絶品とはなるまい。シェフが腕をふるって調理してはじめて美味しい料理は生まれる。「インフォーメーション」がいくら揃っていても、精緻な分析が施されなければ「インテリジェンス」には高められない。素人が新鮮な素材をあれこれ弄んでも、賓客に供する料理は生まれない。
著者のウォルター・シャイブは、その機微を心得ていたのだろう。自分は一流のシェフだが、プロフェッショナルな書き手でも、政治研究者でもないことを。彼はただアメリカの饗宴外交にまつわる活きのいい素材を提供することに徹した。しかも斥候兵の良質な「諜報報告」ともいうべきレシピをふんだんに添えている。これほどの材料が揃っていれば、ホワイトハウス政治にまつわるシーンなど描かれていないほうがいい。情報感覚が研ぎ澄まされた読み手なら、本書から上質なインテリジェンスを存分に絞り出すことができるはずだ。
政治の街ワシントンでは、時の大統領とどれほどの距離にあるかがすべてを決める。とりわけホワイトハウスに在っては、大統領夫妻にアクセスできない者は存在しないに等しい。何万倍の競争を勝ち抜いて『大統領の料理人』の座を射止めたウォルター・シャイブも、クリントン大統領夫妻を幾重にも取り囲む障壁と格闘しなければならなかった。クリントン夫妻へのアクセスに躓けば、饗宴の演出などできないからだ。それゆえ、ホワイトハウスで働くすべての人が、新たにやって来たシェフが大統領夫妻とどんな間合いを築くのか、じっと注視していたのである。一条の光が差し込んできたのはヒラリー・クリントンの思わぬ来訪からだった。
「クリントン夫人が珍しくキッチンにやってくると、私の横で四十五分ほど立ち話をしていった」
クリントン・ホワイトハウスに君臨する権力者は、旧来のフランス料理のメニューに替えてアメリカ独自の食材をふんだんに使った現代風のアメリカ料理を取り入れ、国賓を迎えるステート・ディナーを刷新してみせると公言していた。だが、ヒラリー・クリントンは新参者のシェフと、野球の話題やウエスト・ヴァージニアを話題にしたに過ぎなかった。ファースト・レディが新たに雇い入れたシェフに示した「親しげな態度」こそ、すべてだった。私のシェフに抗う者には「ヒラリーの鉄槌」がくだることを覚悟しなさい―。そんなメッセージが一瞬にして白い館を駆け抜けていった。これがホワイトハウスの「ゲームのルール」なのである。
お気に入りのシェフを迎えないうちは、ステート・ディナーは行わない。こう宣言していたヒラリー・クリントンが、最初に迎えた賓客が平成天皇だった。この歴史的な晩餐会の席でメインディッシュとして供されたのは「アークティック・チャーのロブスターソーセージ添え」だった。北極産のイワナである。主賓のお国柄にちなんだ料理を少なくとも一品は用意してほしい。これがヒラリー・クリントンのシェフへの指示だった。
アリューシャン列島を望む北太平洋で捕れたイワナをメインディッシュに据える。そのことで、太平洋を挟む日米同盟の絆の堅さを表現しようとしたらしい。こんな暗喩は国際政治学者でも汲み取れまい。だがこのエピソードこそ、クリントン政権が対アジア外交でさらけ出してしまった迷走ぶりを物語っているようで、思わず微笑んでしまった。
なるほど『大統領の料理人』は、腕利きのシェフであるだけでなく、クリントン政治の巧まざる語り部だった。