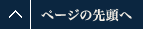「日本人へ リーダー篇」 塩野七生著(文春新書)
揺らぎなき視点
鬱蒼とした森の道を行くと、やがて木造りの尖塔が見えてきた。質素なロシア正教会だった。この教会を取り囲むように鮮やかな色どりの屋並みが森のなかに点在している。十九世紀のロマノフ王朝の町がひっそりと息づいていた。
だが、そこは大都市ニューヨークの通勤圏でもあるロングアイランド半島の亡命者たちの町だった。一世紀近くも前にロシア革命を逃れてサンクトペテルブルクの郊外から移り住んだ白系ロシア人の集落だ。郷里の美しい白樺林が忘れられなかったのだろう。革命で逐われた故郷に似せて同じ街並みを再現し、守護神への堅い信仰を拠りどころに日々の暮らしを営んできた。ロシア正教会のミサで出遭った人たちは、故国では喪われて久しい、端正で古風なロシア語を話していた。
だが、亡命ロシア人の末裔たちは、言語の孤島に閉じこもっていたのではない。新大陸の文明の波にもまれながらも、美しいロシア語を守り育て、豊かな精神を次の世代に伝えていった。烈風にしなうベリョースカ(白樺)にも似て、新しい大地に根を張って、亡命者のコミュニティは生き続けた。その証拠に、ソ連の崩壊後、ここから祖国に再帰還する者が相次ぎ、新生ロシアを担う人材を数多く輩出している。
「文藝春秋」本誌に連載された時には気づかなかったのだが、『日本人へ リーダー篇』として編まれた本書を読んでみると、塩野七生という作家があの亡命ロシア人たちと二重写しになった。日本から遥か離れてイタリアに永く暮らしていることで、故国を見つめる視点に揺らぎがない。明治維新をやり遂げ、先の大戦の廃墟からも立ちあがった日本がなぜいま不振に喘いでいるのか、日本の些事に関わっていないがゆえにその視線は澄んでいる。
森に潜む白系ロシア人の末裔たちに、チェーホフの戯曲の登場人物が棲みついているように、『ローマ人の物語』の著者はユリウス・カエサルを心の友にしている。それだけに、この国から真に指導者の名に値する一群が消えてしまい、国際舞台で日本の存在が軽いものになっている現状に、さぞ歯がゆい思いしていることだろう。だが、塩野七生はもはや既成の政治指導者にではなく、若い世代に希望を託しているようにみえる。日本の明日を担う人々にこれだけは言っておきたい―そんな思いが行間に滲んでいる。
「一級のミリタリーは、一級のシビリアンたれ」と呼びかけた防衛大学校の卒業式での送辞には、塩野七生にもとりわけ思い入れが深かったのだろう。本書にもそのエッセンスが再録されている。
「あなた方も、明日シビリアンの世界に放り出されても、一級のシビリアンで通用するミリタリーになってください。そしてこれが、古今東西変わらない、一級の武人になる唯一の道だと信じます」
この後に「若き外務官僚に」という文章が続き、「拒否権」「常任理事国」「海外派兵も可能な軍事力」「核兵器」「他国に援助可能な経済力」が、現代の国家にとって欠かせぬ五本の剣だと断じている。なかでも「拒否権」こそが最重要の武器だと喝破して見誤らなかった。
「二千年後の現代でも『ヴェトー』というラテン語のままで使われていることが示すように、真の権力とは何かを知り尽くしていた古代ローマ人の発明である」
塩野七生はこう説いて、日本は拒否権という剣を手にした常任理事国の座を自らの手で奪い取れと若き外交官たちを督励した。だが日本の外交当局は、同盟国アメリカさえも味方につけることができず、外交という武器なき戦いに躓いてしまった。チェーザレ・ボルジアを知将として抱える塩野七生にとっては、そのあまりに無様な敗北は正視するに堪えなかったにちがいない。ワシントンの地で日本の国連外交の迷走ぶりをつぶさに見た私には、その怜悧な敗因の分析に脱帽せざるをえない。
「この連載をやめさせてくれと編集長に願い出たら、まだダメですと一蹴された。時間が無いのではない。書くテーマが無いのでもない。それどころか今の日本も世界も問題山積という状態なのだが、それらに立ち向かうのが気が重くなってしまったのだ」
古代ローマをその武力ではなく英知によって築きあげた指導者たちを書き続けてきたこの人の絶望ぶりが伝わってくる。
「危機の時代は、指導者が頻繁に変わる。首をすげ替えれば、危機も打開できるかと、人々は夢見るのであろうか。だがこれは、夢であって現実ではない」
この文章が書かれたのが、小泉政権の時代であることを思えば、この人の言説は、近未来を照射するインテリジェンスの力を秘めていることがわかるだろう。塩野七生は、日本の政治指導者や経済界のリーダーに諫言しているだけではない。主権者たる選挙民へも厳しい警告を発しているのである。
かつて「文藝春秋」本誌でこのひとの対談相手をつとめたことがある。その折、彼女が老舗料亭の女将なら、そこに出入りする客たちは、男を精緻に品定めする眼力に音をあげるだろうと見立てた。だが料亭「塩野」の女将の醒めた視線を浴びて、この国のリーダーたちが震えあがっているうちはまだいい。語るに値する客がいなくなったと嘆いて、早々に店を閉じてしまいはしないか。昨今の政治の現況は、それほどの惨状を呈している