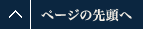危機の財務長官
『ガイトナー回顧録』ティモシー・F.・ガイトナー著
伏見戚蕃訳 日本経済新聞出版社
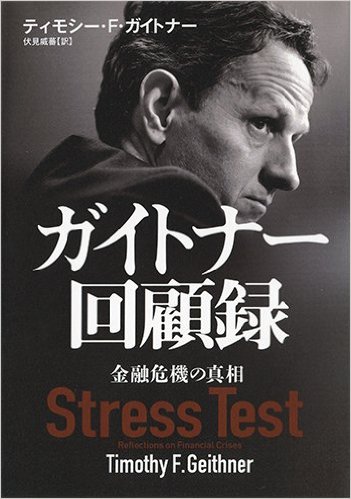 戦争は予期せぬドラマを生む。第二次大戦で敵として戦った不思議の国に魅せられ、日本研究に生涯を捧げることになった人々がいた。ドナルド・キーンもそんなひとりだ。
戦争は予期せぬドラマを生む。第二次大戦で敵として戦った不思議の国に魅せられ、日本研究に生涯を捧げることになった人々がいた。ドナルド・キーンもそんなひとりだ。
戦後の日本もたった一度だけ、各国の知的エリートをわしづかみにした時期がある。80年代の半ば、日本企業は金融力にモノを言わせ、欧米の会社や不動産を次々に買収した。そんなニッポンに惹かれてやってきた若者の一群にティモシー・ガイトナーがいた。
皮肉なことに、彼が90年に目にしたのは、暗く長い不況のトンネルに入ろうとしていた経済大国だった。バブル経済の崩壊から脱却しようにも、誰も決断のリスクをとらない日本がそこにいた。「喪われた20年」と呼ばれ日本の惨状は、後に財務長官となりリーマン・ショックに立ち向かうガイトナーには格好の負の教材となった。
アメリカは日本の轍を踏んではならない――。未曾有の経済危機の処理をオバマ政権の財務長官として委ねられたガイトナーは自らに言い聞かせた。決断をひとたび誤れば、大恐慌を凌ぐ激流が超大国を呑み込み、国際社会をも滝つぼに突き落とす。だが危機の財務長官を苦しめたのは細かな政策手法ではない。アメリカという国を引き裂くふたつの潮流だった。
自由な市場を至高のものとする人々は、巨額の利益を求めてリスクの高い投資に走った金融機関を公的資金で救うべきではないと主張した。政府が介入すれば企業は自らを律することをやめ、モラルハザードが生じてしまうとガイトナーの前に立ちはだかった。
危機の財務長官は、市場の心臓にあたる金融システムが麻痺しかけている時には、公的資金を大胆に投入して金融機関を蘇生させるほか策はないと反論した。
「正しく公平だと思えることは、正しく公平な結果のために必要なこととは逆の場合が多い」
経済危機に際して、決断の神髄を知りたいと考えるときには、論争を巻き起こしている本書をぜひ手にとってもらいたい。