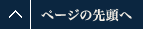「武器なき戦争」の前線に立つ
大野哲弥『通信の世紀 情報技術と国家戦略の一五〇年史』
「カチリ」――石英のぶつかる音に秋の訪れを感じとる。井上靖は旧制中学の友が綴った三行詩に触発され、詩を紡ぎ始めたという。そのひそみに倣っていえば、光ファイバーは微小な石英ガラスを素材に得たことでインターネットの時代を切り拓いた。
いまや地球という惑星の住人の過半が使うインターネット。人々は光ファイバーを介して深く結ばれ、これなしには日々の暮らしは営めないと『通信の世紀』の著者はいう。銅材を使った海底同軸ケーブルなら電話回線にしてわずかに一千。だが光海底ケーブルとなれば数億、いや数十億もの通話が可能となる。
通信回線が世界の風景を塗り替えてしまった現代史の瞬間に立ち会ったことがある。NHKのワシントン支局長として二〇〇一年九月の同時多発テロ事件に遭遇した時のことだ。「テロの世紀」の幕があがるわずか2週間前、大容量の光ファイバー回線が太平洋の海底を通って開通し、ハイビジョン映像を日本に伝送することが可能になった。
超がつく高細密な画像を届ける光ファイバー回線が東京とワシントンを結び、いつ、いかなる時も、ハイビジョン映像によるニュース中継ができる環境が整った。そんな当たり前のことを――といまの若者は思うかもしれない。だが以前は、大事件が起きたらまず中継の衛星を押さえるため、各国の放送局と競わなければならなかった。ケネディ暗殺の衝撃的なニュースも衛星を介して日本に伝えられた。そんな時代がまだ続いていたのである。
自爆テロの旅客機に襲われて炎上する貿易センターと国防総省のハイビジョン映像はいまも人々の脳裏に鮮明に焼きついているはずだ。昼夜にわたって十一日の間続いた中継放送は、光海底ケーブルの存在なしにはあり得なかった。
だが、落とし穴は思わぬところに潜んでいた。光ケーブルはテロ事件の現場となったマンハッタンを経由していたのである。非常用の発電装置で回線は生きていたが、燃料切れの時刻が迫っていた。刻々と生放送を続けながら、代替の衛星を探さなければならなかった。電源が確保され、放送中断の危機は辛くも免れた。光ケーブルは生き残ったのだ。
国際伝送路は、時代とともに海底電信ケーブルから無線通信へ、海底同軸ケーブルから衛星通信へ、さらには光海底ケーブルにと主役が交代していった。著者は「無線対有線の勝負は、有線に軍配が上がっている」という。
本書は技術の変遷を漫然と辿った通信史ではない。「そして対米最終通告は遅れた」の章を読めば、その面白さ、ユニークさがわかるだろう。帝国海軍の空母機動部隊は、開戦通告なしに真珠湾基地に襲いかかった。アメリカのルーズベルト大統領は、十二月七日を「汚辱の日」と呼び、通告なき奇襲を卑劣な振る舞いと難じた。日本政府は最後通牒を用意しておきながら、なぜ、アメリカ政府への通告が奇襲後になってしまったのか。戦後ながく論争は続き、在米日本大使館の怠慢説や奇襲に拘った日本軍の陰謀説が蒸し返されてきた。
だが、本書の著者は極秘電の発着信のタイムラインを詳細に検証し、開戦通告がどうして遅れたのか、その全貌を解き明かしている。東京の統帥部は奇襲を秘匿しようと最後通牒を十四の極秘電に分けて五月雨式に打電していた。在米日本大使館は極秘電を受信しては暗号を解き、英文タイプで清書した。それを読む者は誰しも「もっと急げ」と叫びたくなるだろう。大使館の暗号機を破棄せよと訓令があり、日米開戦は迫っているのに、緊張感のなさは驚くばかりだ。
日米交渉の打ち切りを示唆する運命の第十四号電。その解読を優先して、それを携えて米側に手交する判断すらできなかった。大使館上層部の罪は万死に値する。手書きでも口頭でもいい。指定の時間内に終えていれば、「騙し討ち」の批判だけは免れたろうに。訓令の執行を統御できなかった外務本省。臨機応変の行動をとれなかった現地の外交官たち。著者は公電の発着信のシステムを微細に追うことで「複合汚染」の闇を照射している。
日露戦争を戦い抜いた明治と日米戦争に直面した昭和のリーダーたちの落差を思うと言葉を喪ってしまう。誕生間もない明治国家を率いた人々は、出来たての無線を主力艦に装備し、日本と朝鮮半島を海底ケーブルで結んで、来るべき戦いに備えている。通信の戦略的意義をいち早く理解し、国を挙げて取り組んだ明治の先達。彼らがいかに国際感覚に優れ、新しい技術の導入に真摯に立ち向かったことか。通信という武器なき戦いにあって、それを専門家や技術者に委ねてしまうにはあまりの重大事だ――本書は精緻に事実を積み重ねてそう伝えようとしている。
手嶋龍一(外交ジャーナリスト・作家)