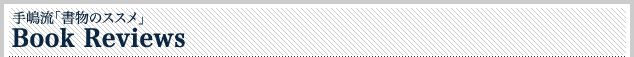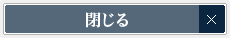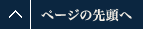20世紀経済史
 「長い20世紀」――現代アメリカを代表する経済史家ブラッドフォード・デロングが紡ぎ出す歴史を貫くキーワードである。19世紀の後半を起点とし、21世紀初めを終点とする140年間こそ、“経済”が最重要の縦糸となった初めての世紀となったという。1870年は、近代的企業が次々に興って技術革新を推し進める環境が整い、それゆえに本格的なグローバル化が始まった年であった。やがて人類は自然を巧みに操り、人間を組織する最新テクノロジーまで生んで、経済が人々を極貧から救い出す原動力となった。あたかも“経済の黄金郷“が出現したかに見えたのだった。
「長い20世紀」――現代アメリカを代表する経済史家ブラッドフォード・デロングが紡ぎ出す歴史を貫くキーワードである。19世紀の後半を起点とし、21世紀初めを終点とする140年間こそ、“経済”が最重要の縦糸となった初めての世紀となったという。1870年は、近代的企業が次々に興って技術革新を推し進める環境が整い、それゆえに本格的なグローバル化が始まった年であった。やがて人類は自然を巧みに操り、人間を組織する最新テクノロジーまで生んで、経済が人々を極貧から救い出す原動力となった。あたかも“経済の黄金郷“が出現したかに見えたのだった。
だが、第一次世界大戦を経てみると、各国の政府は、自己増殖を遂げる凶暴な市場を統御できず、その果てに醜悪なファシズムを生んでしまう。それでも、第二次世界大戦が終わると、世界は再び繁栄を謳歌した。やがて新自由主義の思想が先進国に拡がって金融システムを蝕み、「長い20世紀」は幕を閉じてしまったと著者はいう。それは“アメリカの世紀”の終焉でもあった。
イギリスの歴史学者ホブズボームは、第1次世界大戦の勃発で欧州の旧秩序が崩れた1914年からソ連が崩壊した1991年にいたる期間を「短い20世紀」と表現した。まさしくナチズムとスターリニズムという政治的怪物が荒れ狂った怒涛の世紀だ。熱い戦争と冷たい戦争。その世紀に着目したホブズボームに対抗して、デロングは本書で経済の力が牽引した「長い20世紀」を雄渾に描いてみせた。
史実は手堅く扱いながら、歴史を衝き動かす“見えざる力”に光をあて、現代史をいきいきと語って聞かせる。干からびた出来事の羅列として歴史を教えられたわれわれに歴史講談を語って聞かせるような鮮やかな手並みに息つく暇もない。著者はいまの経済社会を主導するハイテク、なかでも先端半導体の技術に注目する。シリコンウエハーに刻まれた微細な情報群こそ20世紀を切り拓いてきたと喝破した。西海岸の名門大学で経済学を講じるだけでは飽き足らず、国の経済政策を立案し、人気ブロガーとしても最新情報を発信してきた。その多彩な経歴が彼の論議を一層説得力あるものにしている。何より、シリコンバレーの興亡をまぢかで見てきた強みが随所に垣間見える。
デロングが本書で描いた希望と波乱に満ちた「長い20世紀」は本当に幕を閉じたのだろうか。人類は豊かで人間的な暮らしを営むユートピアを夢見た歩みを決してあきらめたわけではないと著者はいう。いまの世界は、アメリカですら悪しき独裁の潮流に呑み込まれようとしている。だが、将来になお希望を捨ててはならないという。
「日本の物語にはまったく度肝を抜かれる」と日本語版序言で述べ、「長い20世紀」でニッポンが果たした成功物語には勇気づけられると記している。同時に、日本は世界の最先端をいく製品を産み出すことができず、日本のイノベーションをグローバル化できなかったと手厳しい。ニッポンの将来は「国としての政策の優先順位とグローバル経済からの圧力のせめぎ合いの中で正しく舵取りできるかどうかに懸かってくる」と警鐘を鳴らす。
その意味でいま熊本と北海道で試みられている先端半導体づくりの挑戦がいかに重要な意味を孕んでいるか分かるだろう。日本ほど整った環境に海外から気鋭の“人財”を迎え入れ、新たな価値を秘めた製品を世界に届けることができるか。いまこそ日本の真価が問われていると著者はエールを送っている。