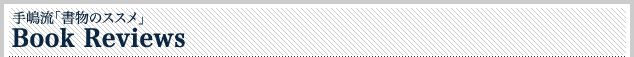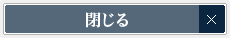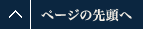トランプ再登場 どう向き合うか
 戦争博物館だけは見ておくといい――駐ベトナム大使だった小倉和夫は、ハーバード大学・代表団の一員としてハノイを訪れた私に是非と勧めてくれた。同行の予定だった陸、海、空軍の高級幕僚は国防総省の許しが出ず現地入りを果たせなかった。ベトナム戦争の傷がなお癒えていない1995年のことだった。
戦争博物館だけは見ておくといい――駐ベトナム大使だった小倉和夫は、ハーバード大学・代表団の一員としてハノイを訪れた私に是非と勧めてくれた。同行の予定だった陸、海、空軍の高級幕僚は国防総省の許しが出ず現地入りを果たせなかった。ベトナム戦争の傷がなお癒えていない1995年のことだった。
「陳列ケースにぽつんと置かれたバリカンと剃刀。床屋に偽装してサイゴンに潜入した解放戦線の戦士が高官の首を掻っ切ったという。これらの凶器にはこの国の凄まじいばかりの忍耐と智慧が凝縮されている」
共産勢力から自由主義陣営を守り抜く。そんな高邁な理想を掲げて軍事介入に踏み切った米国の前に立ちはだかったのは、ホーチミン率いる鋼鉄の決意を秘めた国だった。剃刀に込められたアジアの抵抗の勁さを喝破した著者の慧眼は、超大国の脆さも見誤らなかった。
その4年前、クウェートに突如侵攻したイラクを撃つため、米国は多国籍軍を糾合し立ち上がった。だが、冷戦の勝者も単独では戦費を賄うことがかなわず、極東のニッポンに頼らざるを得なかった。当の経済大国は中東の原油に深く依存しながら、血も流さず、汗も流そうとしなかった。その果てに全てをカネで済まそうとした。外務省の要職にあった小倉は「外交フォーラム」誌上に「理念の帝国と喪失の民との亀裂」を発表した。
「米国は日本に頭を下げて依頼しているのではなく、日本は米国と理念を共有するが故に、日本は自ら進んで自分のために金を用立てし、また技術を提供している――米国としてはこう考えたいのである」
この小倉論文はニューヨーク・タイムズ紙にも取り上げられ、日米同盟の推進役である外務省からも“嫌米派”が現れたと報じられた。私はNHKのワシントン特派員として日米の軋轢を目の当たりにし、『一九九一年 日本の敗北』を著して、日本外交の迷走ぶりを検証した。当時の日本は危機感が驚くほど希薄であり、多額の戦費すら出し渋ったのが真相だった。しかし研究者もメディアも小倉ほど事態の真相には迫れなかった。それだけにこの論考が本書に収録された意義は大きい。
「アメリカ人にとって、アメリカ人たることが一つの信条や信念の問題であるのに対して、日本人にとって、日本人たることは信条や信念の問題ではない――ここに、日米間で大きな誤解と摩擦が生じる一つの基本的原因が横たわっている」
外交の表舞台にあっては、自由な政治制度や市場経済システムは、太平洋を結ぶ盟約を支える礎だとされてきた。そんな崇高な理想の裏に埋もれた現実を小倉は鮮やかに照射してみせた。本人も日米交渉の最前線に身を置きながら、能でいうワキに徹して、日米同盟の素顔を脇から怜悧に見つめていたのである。それゆえ本書の副題を「表と脇と裏舞台」とし、外交の全貌を描き出している。
トランプという異形の大統領が再び表舞台に返り咲き、日米同盟にも烈風が吹き荒れつつある。アメリカの国益を剥き出しで追及する政治リーダーが再登場したことで、自由で開かれた経済システムを先導してきた”理想の王国“は姿を消してしまった。ならば、米国の理念に必死で身の丈を合わせようとしてきたニッポンはどう振る舞えばいいのか。四半世紀前、日米摩擦の本質を解き明かす座標軸を提示した小倉は、理念を喪失した超大国を相手にいかに対峙するべきか、新たな論考を世に問う重い責務がある。