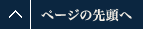阿部重夫が読む 手嶋龍一「スギハラ・ダラー」
越境するマネーの現実と奇想
熊本日日新聞
手嶋龍一はカメレオンである。ときに事実を追うハンターとなり、ときに奇想を紡ぐドリーマーになる。その現実と奇想の交点に本書はある。
彼のアバター(分身)が、京都や金沢の茶屋で遊ぶ数寄者の英国情報機関員スティーブン・ブラッドレー、すなわち本書の主人公だろう。
このアバターは、前作『ウルトラ・ダラー』では北朝鮮の偽ドル札を追った。その続編の本書では、金融先物の最先端シカゴと、ユダヤ人難民六千人を救った「日本のシンドラー」杉原千畝を結びつけた。息をのむような離れ業だ。
そこに浮かぶのは、マネーの本質である「越境性」――すなわち国民経済を担保とするマネーが、国境を越えたグローバル性を得ようとする矛盾である。
ギリシャなどPIIGSと言われる財政危機の国々の「ソブリン・リスク」が世界を震撼させている今、これはぞっとするほどアクチュアルなテーマだ。
リーマン危機で戦後の通貨制度を定めたブレトンウッズ体制が揺らぎ、一九七一年に変動相場制に移行したドルが基軸通貨の座を維持できるかどうか、試されている。
GDP(国内総生産)比の累積債務残高が200%に接近する日本も、潜在的には被告台に立たされている。グローバル化を拒んだ円が国際通貨の座を失いかけているからだ。
本書が単なる奇想でないのは、現実のモデルという錨があるためだ。それを憶測しながらでないと、虚実の境に立つ本書を読み解く楽しみは半減する。杉原千畝が単なる人道派の外交官ではなく、敵国ロシアの背後でインテリジェンス工作に身を挺していたことは紛れもない事実である。
ソ連の暗号を解読し、冷戦期にソ連のスパイ工作を暴露した「ヴェノナ」作戦が、フィンランドと日本の戦時中の交信を傍受して突破口をみつけたように、ソ連に呑みこまれる直前のバルト海の情報戦争は熾烈を極めた。
杉原ビザで救われて神戸にたどりつく難民の少年アンドレイは、シカゴ・マーカンタイル取引所のドンとなったレオ・メラメドだろう。その親友となる日本人相場師、雷児はたぶん是川銀蔵がモデルだろうが、そのスケールはむしろアメリカからスイスに亡命した伝説のトレーダー、マーク・リッチのほうがふさわしい。
シカゴが表なら、リッチは裏である。ベルギー系ユダヤ人の出身で、今日の石油投機の基礎を築いた。七九年のイラン革命後に禁輸を破って、イラン産石油をイスラエルに密輸している。アメリカの逆鱗に触れ、暗殺対象になった。
カストロのキューバ、内戦のアンゴラ、アパルトヘイトの南アフリカなど、経済制裁の網をくぐる密輸の裏には、常にリッチの影がちらつく。アルカイダなどの国際テロ組織も、その地下ルートに塊茎のごとく連なっている。
マネーの「越境性」はそこに聖なる秘密がある。欠席裁判で天文学的な懲役判決を受けたリッチは、クリントン政権末期に巨額の政治献金を積んで大赦を勝ちとった。その彼が長年の沈黙を破って、雑誌編集者のインタビューに応じ、なぜ生き残れたかを語った本(The King of Oil ; The Secret Lives of Marc Rich)が昨年出版された。
やはりと言うべきか、彼の生命を守ったのはイスラエル情報機関だった。
本書にも、イスラエルを防衛しようとマネーの聖域に身を投じる美少女ソフィーが出てくる。それもリッチのアバターと言えよう。マネーの聖性は地下に潜む。